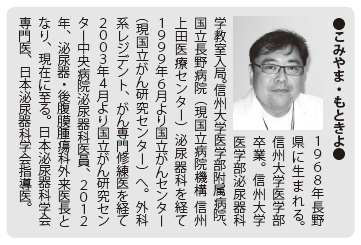がん治療(標準治療)の基礎知識
治療の流れを理解し、より適切な治療を受けるために
第8回 腎臓がん
早期腎臓がんは健康診断などで偶然見つかる
腎臓は腹部の背中寄りに位置する左右一対の臓器で、主に血液から老廃物を濾ろ過かして尿をつくる働きをしています。その他、ホルモ
ンを分泌して血圧や尿量を調節したり、ビタミンDを活性化したりする役割を担っています。
一般に「腎臓がん」という場合には、腎細胞がんのことを指します。腎細胞がんは、尿を生成する機構の一部である近位尿細管の細胞が、がん化した病気です。
腎臓がんは、早期の段階では、自覚症状が現れることはほとんどありません。そのため、症状から腎臓がんを早期に発見することはできません。しかし、最近は早期に見つかる腎臓がんが増えています。CTやMRIなどの画像検査が進歩したことや、健康診断を受ける機会が増えたことで、他の病気の精密検査などを行ったと
きに、腎臓がんが小さなうちに偶然見つかることが増えているのです。
また、がんの進行や転移に伴って、貧血、倦怠感、発熱、食欲不振などの症状や、肺転移、骨転移による骨折、脳転移に伴うけいれんなどの症状が現れ、腎臓がんが発見されることもあります。
腎臓がんの診断に有用な2種類の画像検査
腎細胞がんの疑いがある場合、まず行われる検査は、「ダイナミックCT検査」と「腹部超音波検査」です。
ダイナミックCT検査は、CT検査の際に造影剤を急速静注し、動脈相、平衡相、遅延相と時間をずらして撮影します。典型的な腎臓がんの画像(図1)
![図1 腎細胞がんの診断 dynamicCT検査による腎細胞がん(矢印で指しているのが腫瘍)[第8回 がん治療(標準治療)の基礎知識 腎臓がん]](https://gan-senshiniryo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/201507_18_kidneycancer_1.gif)
では、動脈相では腎皮質と同様に腫瘍も強く染まりますが、平衡相~遅延相にかけては、腎実質よりも早く造影剤が排泄されるため暗く見えるのが特徴的です。
腹部超音波検査は、健康診断の際にもよく行われる検査ですが、腎臓の腫瘍に対しては超音波による見え方の特徴により、性質の診断を行います。また超音波検査では臓器の動きも観察できるため、手術に向けて周辺の臓器との関係を診断します。
この2つの検査によって、典型的な腎臓がんであれば、診断に必要な情報を得ることができます。腎臓がんであると判断できた場合には、手術前に病理診断* は行われません。
ダイナミックCT検査と腹部超音波検査で診断がつかない場合には、必要に応じてMRI検査が行われます。それでも判断がつかなければ、体の外から腫瘍に針を刺し、組織を採取する生検が行われることがあります。
腎臓がんと診断がついたら、治療方針を決めるために、病期(がんのステージ)診断と全身状態の確認が行われます。
病期診断のためには、転移の有無が調べられます。腎臓がんが転移しやすいのは、肺、リンパ節、肝臓、膵臓、骨などです。これらの転移を調べるのに有用なのは「CT検査」です。
これに、脳の転移を調べる「脳MRI検査」や、骨の転移を調べる「骨シンチグラフィ」などの検査が追加されることもあります。
さらに血液検査、尿一般検査、尿細胞診検査を行います。血液検査では腎機能の評価や、予後を占う因子として、血清カルシウム値、貧血の有無、CRPやLDHの異常などが調べられます。
*病理診断:患部から採取された組織の一部を顕微鏡で観察し、病変の有無、種類、性質などを見分けること。
手術できるかどうかを見分けることが大切
腎臓がんの病期(ステージ)は、原発巣の広がり(T1~T4)、
所属リンパ節転移の有無と個数(N0~N2)、遠隔転移の有無(M0、M1)によって判定します(表1)。
![表1 腎細胞がんの病期分類(腎癌取り扱い規約2011年4月[第4版])[第8回 がん治療(標準治療)の基礎知識 腎臓がん]](https://gan-senshiniryo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/201507_18_kidneycancer_2.gif)
ただし、病期の診断がついても、それだけで治療方針が決まるわけではありません。切除手術が可能か不可能か、遠隔転移があるかないかによって、腎臓がんの治療戦略は決まってきます(表2)
![表2 腎細胞がんの治療戦略[第8回 がん治療(標準治療)の基礎知識 腎臓がん]](https://gan-senshiniryo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/201507_18_kidneycancer_3.gif)
遠隔転移がない腎臓がんに対する最も適切な治療は、「手術療法」です。しかし、がんが重要な臓器や血管に浸潤している場合などには、切除ができない場合もあります。
遠隔転移が発見されている場合には、それ以外の場所にもすでにがんが転移している可能性もあるため、基本的には手術の適応はないと考えられてきました。しかし遠隔転移が発見されていても、がんのある腎臓の切除が可能であれば行ったほうが予後が良いともいわれてきています。各々の状況により方針は異なりますが、薬物療法と手術療法を組み合わせた治療も試されています。
腫瘍が切除できない場合や、遠隔転移がある場合には、基本的に全身を対象とした「薬物療法」が選択されます。
手術には腎全摘除術と腎部分切除術がある
腎臓がんが腎臓内に限局している場合には、がんのある側の腎臓を、腫瘍とともに切除する手術が行われます。この手術は「腎全摘除術(根治的腎摘除術)」と呼ばれ、腎臓がんの最も標準的な手術です(図2)
![図2 腎摘除術(右腎を例とした)[第8回 がん治療(標準治療)の基礎知識 腎臓がん]](https://gan-senshiniryo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/201507_18_kidneycancer_4.gif)
ステージⅠとステージⅡの場合、この手術による治療成績は良好で、10年疾患特異生存率(10年間腎臓がんで死亡せずに生存している人の率)は、それぞれ90%、80%に及ぶ報告がほとんどです。
小さな腎臓がんに対しては、がんとその周囲の腎臓を一部切除する「腎部分切除術」が、広く行われるようになっています(図3)
![図3 腎部分切除術(右腎を例とした)[第8回 がん治療(標準治療)の基礎知識 腎臓がん]](https://gan-senshiniryo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/201507_18_kidneycancer_5.gif)
腎機能を温存できるのが、この手術法の優れている点です。
どのような腎臓がんが腎部分切除術の対象となるのか、基準は定められていません。施設によってさまざまな基準が設けられていますが、国立がん研究センター中央病院では、腫瘍径が3㎝以内、かつ腫瘍が内側で腎じ んどう洞に接していない、形態的に切除可能である、ということをおよその基準として、腎部分切除術を行っています。
この基準を満たしている場合、腎部分切除術の治療成績は、腎全摘除術と比べて遜色がなく、腎部分切除術はすでに標準治療となっています。
腎臓に達する方法としては、開腹手術と腹腔鏡(後腹膜鏡)下手術があります。腹腔鏡(後腹膜鏡)下手術の主な対象は早期のがんです。腎臓に対する処置はどちらの手術でも同じですが、腹腔鏡(後腹膜鏡)下手術のほうが傷を小さくできます。
手術ではありませんが、局所的な治療として「凍結療法」が行われることがあります。小さながんに、体の外側から針を刺し、がんを凍らせて処理する治療です。身体に与える侵襲は小さいことが利点ですが、根治性に関してはまだ不明の部分があります。
6種類の分子標的薬を使うことができる
腎臓がんの薬物療法には、「インターフェロン」による治療と、最近になって登場してきた「分子標的薬」による治療があります。
インターフェロンによる治療の奏効率(治療後にがんが縮小したり消滅したりする患者の割合)は、わずか15~20%程度です。それが現在でも使われているのは、効く人は少ないのですが、効いたときには、劇的な効果をもたらすことがあるからです。また日本人は欧米人に比べ、インターフェロンが効きやすいこともわかっています。
また、近年登場してきた「分子標的薬」が腎臓がんに効果があることがわかってきました。腎臓がんには通常の抗がん剤はあまり有効ではありません。しかし、分子生物学の研究が進み、がんの転移や増殖に関わる標的分子が特定されてきました。この分子の働きを制御する薬剤「分子標的薬」の開発が進められ、治療に用いられるようになってきました。
腎臓がんの治療に使用が認められている分子標的薬は、
次の6種類です。作用機序により、チロシンキナーゼ阻害
薬とmTOR阻害薬の2種類に分類されています。
◆チロシンキナーゼ阻害薬
・スニチニブ(sunitinib)
・ソラフェニブ(sorafenib)
・アキシチニブ(axitinib)
・パゾパニブ(pazopanib)
◆mTOR阻害薬
・エベロリムス(everolimus)
・テムシロリムス(temsirolimus)
これらの薬剤による治療は、インターフェロンに比べて奏効率が高く、40%程度です。数カ月の予後延長効果があることもわかっています。
これらの薬剤による治療は、インターフェロンに比べて奏効率が高く、40%程度です。数カ月の予後延長効果があることもわかっています。
これらの分子標的薬を、どのような順番で使用するのが最も効果的なのか、現在の段階では、まだ結論が出ていません。それを明らかにするために、さまざまな研究が進められています。
一般的に分子標的薬による治療は、遠隔転移や再発病変もしくは切除不能な腎臓がんに用いられます。よって、手術後の再発予防目的として用いられることの効果はまだわかっておらず、通常は用いられません。
なお、遠隔転移のある進行腎臓がんに対しては、予後を予測する目的でリスク分類(Motzercriteria)が唱えられています。「KPS(全身状態)が80%未満」「血清LDH(乳酸脱水素酵素)値が正常上限の1・5倍以上」「ヘモグロビン値が正常下限値未満」「補正血清カルシウム値が10㎎/ dL 以上」「腎臓がんと診断されてから1年未満」という5つの予後因子のうち、いくつに当てはまるかで、リスク分類するのです。
当てはまる予後因子が0個なら低リスク、1~2個なら中リスク、3個以上なら高リスクと判定します。このリスク分類が、分子標的薬の選択に利用されることもあります。
放射線療法は転移巣に対する治療で使われる
腎臓がんは放射線が効きにくいがんです。そのため、手術の代わりに根治目的で、腎臓に対して放射線療法が行われることはありません。放射線療法が行われるのは、脳転移や骨転移に対する治療です。脳転移に対してはサイバーナイフが、骨転移に対しては疼痛緩和や骨折予防などの症状コントロールを目的として放射線照射が行われます。他の部位に対しても、症状緩和を目的として、放射線療法が行われることがあります。