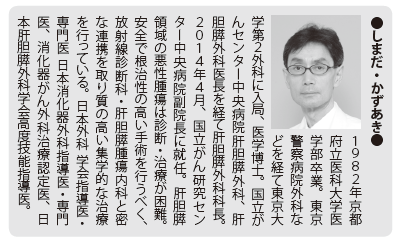がん治療(標準治療)の基礎知識
治療の流れを理解し、より適切な治療を受けるために
第6回 胆道がん
胆道がんの基礎知識
胆道がんは、胆汁の通り道である胆道に発生するがんの総称です。胆汁は肝臓でつくられ、最終的に十二指腸に排出されます。その間をつないでいるのが胆道で、各部位に名称がついています(図1)。
![図1 肝外胆管の区分・名称 日本胆道外科研究会/編 外科・病理胆道癌取扱い規約2003年9月【第5版】東京 金原出版より抜粋[第6回 がん治療(標準治療)の基礎知識 胆道がん]](https://gan-senshiniryo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/201504_17_biliarytractcancer_1.gif)
肝臓でつくられた胆汁は、肝臓内に張りめぐらされた肝内胆管によって集められます。そして、肝臓外の肝門部胆管、上部胆管を通り、胆のう管と合流して中下部胆管へ流れていきます。下部胆管は、膵臓内を通る膵管と十二指腸乳頭部で合流し、胆汁は膵液とともに十二指腸に排出されます。中下部胆管を遠位胆管と呼ぶこともあります。
胆道がんは、胆のうを含めた胆汁の通り道にできるがんですが、肝内胆管がんは、肝臓がんに含める場合と、胆道がんに含める場合があります。ここでは、肝門部から乳頭部までにできる胆道がんを中心に解説します。
胆道がんの多くは、黄おうだん疸などの症状が出ることで発見されます。がんによって胆汁の通り道が塞がれると、停滞した胆汁に含まれる色素が血液中に入り、皮膚や白目の部分が黄色く変色する黄疸という症状を引き起こすのです。したがって、がんがどこにできるかによって、黄疸の現れ方は違ってきます。胆道の下流にできると症状が現れやすく、肝門部の合流点より上や胆のうにできると、症状が現れにくいという特徴があります。
組織診を行うことが推奨されている
胆道がんの診断は、3段階に分けて進められます(図2)
![図2 診断手順のフローチャート[第6回 がん治療(標準治療)の基礎知識 胆道がん]](https://gan-senshiniryo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/201504_17_biliarytractcancer_2.gif)
まず行われるのは、血液検査と腹部超音波検査です。それに加え、CT検査とMRI検査が行われます。CT検査は、3次元画像が得られるMDCT検査が広く行われています。
CT検査などの画像検査で腫瘍の有無、できている位置や大きさを調べた後、黄疸がある場合には、黄疸に対する治療が行われます。その際に、がんの組織を採取し、それを顕微鏡で調べる組織診を行うことが推奨されています。
画像検査では腫瘍のように見えても、炎症性変化や、結石が合併して胆管が詰まる場合もあります。そこで、組織を調べ、がんであることを確認するのです。ただし、胆のうにできている場合は組織の採取が困難なので、胆管のがんほど組織診を強く推奨されているわけではありません。
胆道がんであることが明らかになったら、治療を進めるために、超音波内視鏡検査などの精密検査が行われる場合もあります。
黄疸を治療することで肝臓機能を回復させる
黄疸がある場合、それに対する治療が行われます。がんによって、胆汁の通り道が塞がれ肝臓の機能が低下するため、そのままでは手術や抗がん剤による治療を行うのが難しいからです。黄疸に対する治療を減黄処置といいます。
減黄処置には、ERBD(内視鏡的逆行性胆管ドレナージ)と、PTBD(経皮経肝胆管ドレナージ)という方法があります(図3)
![図3 黄疸の治療[第6回 がん治療(標準治療)の基礎知識 胆道がん]](https://gan-senshiniryo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/201504_17_biliarytractcancer_3.gif)
ERBDは、内視鏡を口から十二指腸まで入れ、乳頭部から胆管にチューブを挿入して、それを閉塞部の上流まで送り込み、胆汁が十二指腸に排出されるようにします。胆汁の流れを確保するため、胆管内にステントを留置します。技術的にPTBDほど難しくないので広く行われていますが、まれに重症な膵炎を起こす危険性があります。
PTBDは、超音波画像を見ながら体表から肝臓内に細いチューブを入れ、そこから拡張している胆管までチューブを送り込みます。そして、たまっている胆汁を体外に排出させます。技術的に難しいのと、胆汁を体外に誘導するため、患者さんは一時的に生活が不便になるのが欠点です。ただ、黄疸を確実に治療でき、膵炎などのリスクはありません。
胆道がんの手術法は、がんの部位で異なる
胆道がんの治療で唯一完治が期待できるのは切除手術です。そこで、治療手順としては、まず切除手術が可能かどうかを判断します(図4)
![図4 標準治療手順のフローチャート[第6回 がん治療(標準治療)の基礎知識 胆道がん]](https://gan-senshiniryo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/201504_17_biliarytractcancer_4.gif)
手術が可能なら手術が行われ、手術ができなければ、化学療法や放射線療法が行われます。
手術できないと判断されるのは、がんが広範囲に広がり重大な血管に浸潤(がんが広がること)している場合、肝臓や肺といった遠隔臓器や大動脈周囲のリンパ節に転移している場合、腹膜にがんが散在する腹ふ くまくはしゅ膜播種が認められる場合などです(図5)。
![図5 外科切除が不可能な因子[第6回 がん治療(標準治療)の基礎知識 胆道がん]](https://gan-senshiniryo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/201504_17_biliarytractcancer_5.gif)
手術可能な場合、手術の方法は、がんのできている部位によって異なります。
「肝門部・上部胆管がん」「胆のうがん」「遠位胆管がん・乳頭部がん」に分けて解説します。
◆肝門部・上部胆管がんの手術
肝門部胆管や上部胆管にがんができている場合には、拡大肝右葉切除(あるいは拡大肝左葉切除)と肝外胆管切除を併せて行うのが標準的な手術です。拡大というのは、片葉だけでなく、尾状葉を含めて切除することを意味しています。
肝臓は右葉が全体の6~7割を占め、左葉が3~4割を占めています。そのため、左葉の切除は問題ありませんが、右葉を切除する場合には、肝臓の働きが低下する心配があります。そこで、左葉を十分に肥大させてから手術を行います。右葉に行く門脈という血管を塞そくせん栓物質で詰まらせると、血液は左葉にだけ流れていき、左葉が従来よりも肥大してくるのです。これを門脈塞栓術といいます。2~3週間かけて左葉を肥大させてから、右葉を切除する手術が行われます(図6)。
![図6 拡大肝右葉切除の切除範囲と再建[第6回 がん治療(標準治療)の基礎知識 胆道がん]](https://gan-senshiniryo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/201504_17_biliarytractcancer_6.gif)
◆胆のうがんの手術
粘膜にとどまるような早期のがんであれば、胆のうを切除する単純胆摘術が行われます。漿し ょうまくかそう膜下層以上に進行している場合には、肝臓の一部を合併切除しリンパ節郭清を伴った拡大胆摘術が標準的な手術です。
胆管に浸潤している可能性がある場合や、リンパ節転移がある場合には、肝外胆管切除を追加します。
胆のうがんが進行し、胆外胆管や肝動脈に浸潤している場合には、肝門部胆管がんの場合と同様に、拡大肝右葉切除・肝外胆管切除が行われます(図7)。
![図7 胆嚢がんと拡大胆摘術[第6回 がん治療(標準治療)の基礎知識 胆道がん]](https://gan-senshiniryo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/201504_17_biliarytractcancer_7.gif)
膵頭部(すいとうぶ)や十二指腸へ浸潤している場合には、下部胆管がんの場合と同様に、膵頭十二指腸切除(説明後述)が行われることがあります。
◆ 遠位(中下部)胆管がん・乳頭部がんの手術
下部胆管が膵臓内を通るため、遠位胆管がんや乳頭部がんは膵臓に浸潤することがあります。そこで、膵頭部と十二指腸を切除する膵頭十二指腸切除が標準的な手術です。切除後は、残った膵臓、胆管、胃を小腸とつなぎ、胆汁や膵液が小腸に流れるように再建します(図8)。
![図8 全胃温存膵頭十二指腸(PPPD)切除術と再建[第6回 がん治療(標準治療)の基礎知識 胆道がん]](https://gan-senshiniryo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/201504_17_biliarytractcancer_8.gif)
中部胆管に限局している早期の胆管がんは、肝外胆管だけを切除する肝外胆管切除が行われる場合もあります。ただし、このようなケースは多くはありません。
また、早期に発見された乳頭部がんの場合には、経十二指腸的乳頭切除や、内視鏡的切除が行われます。
再発を防ぐ治療はまだエビデンスがない
進行胆道がんは再発が起こりやすく、画像検査で見えているがんをすべて取り除いても、再発することがあります。再発を防ぐための術後補助化学療法に関しては、これまでのところ明確なエビデンス(科学的根拠)がありません。現在、臨床試験が進められています。結果が出るまでには、まだ数年かかりそうです。
ただし、リンパ節転移があるなど、再発のリスクが高いと考えられる場合には、術後補助化学療法を行っている施設も多くあります。抗がん剤としては、ゲムシタビンやS‒1が使われています。
手術後5年間は定期的な検査が必須
胆道がんの手術は比較的大きな手術ですが、経過が順調であれば、術後2~3週間で退院となります。膵頭十二指腸切除の場合でも、術後の回復も早く、QOL(生活の質)も比較的良好な状態に保たれます。肝臓を大きく切除した場合、多少時間がかかりますが、日常生活に支障のないレベルまで体力が回復します。
術後5年間は再発の危険があるため、定期的にCT検査を受ける必要があります。再発は2年目までが多いので、2年間は3~4カ月おき、その後は6カ月おきに検査を受けます。
手術不能例や再発にはGC療法が標準治療
切除手術の対象とならない場合や、手術後に再発した場合には、全身疾患と考えて抗がん剤による治療が行われます。標準治療とされているのが、ゲムシタビンとシスプラチンという抗がん剤を併用するGC療法です。強い副作用はありませんが、吐き気、倦怠感、食欲不振、骨髄抑制(白血球減少、血小板減少、貧血)などが出ることがあります。
現在、胆道がんの治療薬として認可されている抗がん剤は、ゲムシタビン、シスプラチン、S‒1、テガフール・ウラシル、シラタビン、ドキソルビシンです。また、オキサリプラチンのように、臨床試験で有用性が証明され、期待されている抗がん剤もあります。
放射線療法は手術で取れない場合に行われる
初回治療で放射線療法が選択されるのは、がんは局所にとどまっているが、手術では取れないようなケースです。ただ、この場合でも根治的な治療ではなく、治療の目的は進行を抑えることになります。術後の再発で、再発部位が局所にとどまっている場合にも、放射線療法が行われることがあります。