がん治療(標準治療)の基礎知識
治療の流れを理解し、より適切な治療を受けるために
第5回 肝臓がん
肝臓がんの死亡率は低下している
肝臓に発生するがんには、肝臓の細胞から発生する肝細胞がんの他に、肝臓に張りめぐらされている胆管から発生する胆管細胞がんもあります。ここでは、肝臓にできるがんの大部分を占めている肝細胞がんを、「肝臓がん」として解説します。
肝臓がんの発生数はずっと増えてきましたが、数年前から減少に転じ、死亡率も低下してきました。
肝臓がんは、ほとんどの場合、超音波検査で発見されます。発見された後、CT検査で詳しく調べます。CT検査の代わりにMRI検査が行われることもあります。
これらの画像検査で、がんかどうかも診断します。細胞や組織を採取して調べる生検は行いません。肝臓がんは風船を膨らませたような構造なので、針を刺すと、がん細胞が周囲に漏れ出ることがあります。そのリスクが大きいため、生検は行われないのです。
肝障害度、がんの個数、がんの大きさなどから適切な治療法を選択
肝臓がんの病期(ステージ)は、腫瘍の個数、大きさ、脈管侵襲の有無、リンパ節転移の有無、遠隔転移の有無により、Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期、ⅣA期、ⅣB期に分類されます(図1)。
![図1 肝臓がんの病期分類[第5回 がん治療(標準治療)の基礎知識 肝臓がん]](https://gan-senshiniryo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/201504_17_livercancer_1.gif)
ただし、これだけでは、肝臓がんの治療方針を決定することはできません。肝臓がんの治療選択では、肝臓の機能がどの程度損なわれているかを示す「肝障害度」も考慮する必要があります。肝障害度は、A、B、Cの3段階に分類されます(図2)
![図2 肝障害度 肝機能の状態は、腹水、血清ビリルビン値、血清アルブミン値、インドシ アニングリーン染色テスト(ICG)15 分値、プロトロンビン活性値の5項目を総合的に判断し、ABC の3段階で評価される。[第5回 がん治療(標準治療)の基礎知識 肝臓がん]](https://gan-senshiniryo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/201504_17_livercancer_2.gif)
肝臓がんの多くは、慢性肝炎や肝硬変の肝臓に発生してくるため、肝機能が損なわれていることが少なくありません。また、肝臓は欠かすことのできない臓器のため、すべてを摘出することはできず、治療後に十分な肝機能が残っている必要があります。そのため、肝臓がどの程度障害されているかにより、選択できる治療法が変わってきます。
肝障害度、がんの個数、がんの大きさから、適切な治療法が選択されます(図3)
![図3 肝臓がんの治療法[第5回 がん治療(標準治療)の基礎知識 肝臓がん]](https://gan-senshiniryo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/201504_17_livercancer_3.gif)
肝障害度がCの場合には、緩和ケア以外に治療の方法がありません。肝障害度がAかBの場合には、「手術」「ラジオ波焼しょうしゃく灼療法」「肝動脈化学塞そくせん栓療法」「化学療法」といった治療の選択肢があります。
肝機能がよく、がんが3個以内なら、手術を選択
肝臓の切除手術は、肝障害度がAかBで、がんの個数が3個までの場合が標準となっています。がんの大きさは問いません。がんが4個以上あっても切除はできますが、再発する可能性が高くなります。3個までなら、ラジオ波焼灼療法や肝動脈化学塞栓療法と比べても、再発率が低いことがわかっています。
肝障害度に関しては、ガイドラインではAかB となっていますが、最も適しているのはAで、Bの中でも比較的肝機能のよいものが対象となります。
肝臓がんの手術は、肝臓を8つの区域に分け、必要な区域だけを切除する「系統的区域切除」という手術が行われています。
肝臓は右葉と左葉に分かれ、その間に小さな尾状葉がありますが、血液の流れで見ると、8つの区域に分けることができます。各区域には、S(Segment)1〜S8の番号が付けられています(図4)
![図4 肝臓の区域[第5回 がん治療(標準治療)の基礎知識 肝臓がん]](https://gan-senshiniryo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/201504_17_livercancer_4.gif)
S1は尾状葉、S2〜S4は左葉、S5〜S8は右葉です。手術では、がんのできている部位の肝臓を、区域単位で切除します。
肝臓に入っている門脈という血管は、8本に枝分かれして、それぞれの区域に血液を送っています。そのため、系統的に区域単位で切除することにより、手術による肝機能の低下を最小限に抑えることができます。また、血流に沿って区域を切除するため、がんが血流に乗って転移するのを予防するのにも役立っています。
肝臓の切除手術は、かつては大きな身体的負担を伴う治療でした。しかし、手術方法が進歩し、出血を少なく抑えられるようになったことで、身体的負担も軽くなっています。出血が少なく抑えられた場合、1週間ほどで退院できます。
腹腔鏡手術も行われるようになっていますが、標準的な治療法ではありません。腹腔鏡を使わなければ取れない肝臓がんは存在しないことに加え、時間が長くかかり、コストが高い、安全性が確保されていない、といった問題点が指摘されています。
がんが3㎝以下で3個以内なら、焼灼療法を選択可能
ラジオ波焼灼療法は、手術と並ぶ肝臓がんの局所療法です。超音波画像でがんの位置を確認しながら、体の外から肝臓のがんに電極針を刺し、この電極から高周波の一種であるラジオ波を発信することで周囲を高温にします。それによって、がんを死滅させる治療法です(図5)。
![図5 ラジオ波焼灼療法[第5回 がん治療(標準治療)の基礎知識 肝臓がん]](https://gan-senshiniryo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/201504_17_livercancer_5.gif)
この治療法が適しているのは、がんの大きさが3㎝以内で、個数が3個以下の場合です。肝障害度はAかBならよく、手術と比較すると、肝障害度が進んでいても治療できます。
治療によるダメージが少ないのが特徴です。再発しても、3㎝以内3個以下の条件に当てはまっていれば、この治療を繰り返すことができます。
がんが3㎝以上や4個以上なら、肝動脈化学塞栓療法を選択
がんが4個以上ある場合には、手術もラジオ波焼灼療法も原則として適応となりません。この場合、まず選択されるのは肝動脈化学塞栓療法です。また、個数が3個以下でも、大きさが3㎝以上ある場合には、手術かこの治療を選択することができます。肝障害度は、Aと、Bの中でも比較的よい状態のものが適しています。
この治療では、脚の付け根の血管からカテーテルを入れ、それを肝動脈に進めて、がんの近くまで送り込みます。そこで抗がん剤を注入し、塞栓物質で血管を塞ぎます。高濃度の抗がん剤による作用と、肝動脈を塞がれて栄養と酸素が断たれることで、がんを死滅させる治療法です(図6)。
![図6 肝動脈化学塞栓療法[第5回 がん治療(標準治療)の基礎知識 肝臓がん]](https://gan-senshiniryo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/201504_17_livercancer_6.gif)
抗がん剤は、シスプラチンやエピルビシンなどが使われています。
カテーテルの進歩と、カテーテルを送り込む技術の進歩で、がんのすぐ近くまでカテーテルを入れられるようになったため、治療効果が向上し、周囲の組織へのダメージが小さくなりました。この治療を行った後で再発しても、条件に当てはまれば、繰り返し治療を行うことができます。
肝動脈化学塞栓療法は、手術やラジオ波焼灼療法を受け、その後再発した場合に選択されることもよくあります。再発ではがんが多発しやすく、がんの個数が4個以上になってしまうことが多いからです。
化学療法には、肝動注と分子標的薬治療がある
肝障害度がBでも、肝動脈化学塞栓療法を行えないほど肝機能が低下した場合には、肝動脈に送り込んだカテーテルから抗がん剤を注入する肝動注化学療法が行われます。肝動脈化学塞栓療法と違い、塞栓物質で血管は塞ぎません。抗がん剤は、シスプラチンやドキソルビシンが使われています。
遠隔転移があるため、手術や局所療法の対象とならない進行肝臓がんには、分子標的薬のソラフェニブによる治療が有効であることが明らかになっています。プラセボ(偽薬)と比較した臨床試験で、ソラフェニブを使用すると、がんが悪化するまでの期間や生存期間が延長することが確かめられたのです。
ソラフェニブはいくつかの標的分子を持つ薬ですが、中心となっているのは、血管新生阻害作用です。がんが増殖するためには、新しい血管をつくって栄養を取り入れる必要がありますが、その血管ができないようにすることで、がんの増殖を抑えるのです。
再発しやすいので、治療後の定期検診が重要
切除手術の対象とならない場合や、手術後に再発した場合には、全身疾患と考えて抗がん剤による治療が行われます。標準治療とされているのが、ゲムシタビンとシスプラチンという抗がん剤を併用するGC療法です。強い副作用はありませんが、吐き気、倦怠感、食欲不振、骨髄抑制(白血球減少、血小板減少、貧血)などが出ることがあります。
現在、胆道がんの治療薬として認可されている抗がん剤は、ゲムシタビン、シスプラチン、S‒1、テガフール・ウラシル、シラタビン、ドキソルビシンです。また、オキサリプラチンのように、臨床試験で有用性が証明され、期待されている抗がん剤もあります。
放射線療法は手術で取れない場合に行われる
肝臓がんは再発しやすいがんです。手術、ラジオ波焼灼療法、肝動脈化学塞栓療法などで、がんが根治できたとしても、再発してくることがあります。他のがん種の再発は、治療で取り残された微小ながんが、大きくなることで起こります。肝臓がんでは、このようにして起こる再発以外に、新たにがんが発生することが多いのです。
肝臓がんは、慢性肝炎や肝硬変を起こしている肝臓に発生してきます。そのため、がんを取り除くことができても、残された肝臓ががんを発生させやすい状況にあることは変わりません。そして、残っ
ている肝臓に、新たながんが発生することがあるのです。
したがって、再発のほとんどは、まず肝臓に起こります。肝臓に再発した後、遠隔転移を起こすことはありますが、肝臓に再発が見られないまま、遠隔転移が起こることはまずありません。
そこで、治療でがんを取り除くことができた場合、治療後は定期的な肝臓の検査を受け、なるべく早い段階で再発を発見できるようにします。2〜3カ月に1回は超音波検査を受け、1年に2回はCT検査を受けます。それを4〜5年は続けるようにします。再発が起きたときには、初発肝がんと同じ基準で、治療を選択します。
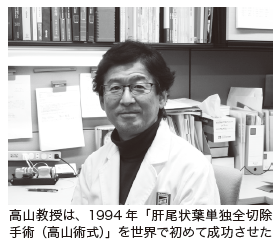

![高山忠利 日本大学医学部長・大学院医学研究科長・消化器外科教授
日本大学医学部部長、消化器外科教授。1980年日本大学医学部
卒業、同大学大学院外科学修了。国立がんセンター中央病院外科医長、東京大学医学部肝胆膵
移植外科助教授を経て、2001年から現職。日本外科学会専門医・指導医・評
議員、日本消化器外科学会専門医・指導医・評議員、日本肝胆膵外科学会高度技能指
導医・評議員など。日本肝臓学会織田賞、東京都医師会賞などを受賞。[第5回 がん治療(標準治療)の基礎知識 肝臓がん]](https://gan-senshiniryo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/201504_17_livercancer_0.gif)







