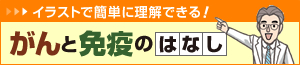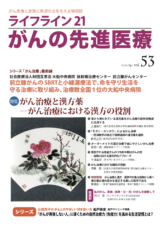(監修:杏林大学医学部泌尿器科教授 桶川隆嗣先生)
2.精巣がんの治療について
- 2-1.精巣がんの治療方針
- 2-2.精巣がんの治療法――1.手術
- 2-3.精巣がんの治療法――2.化学療法
- 2-4.精巣がんの治療で使われる薬剤
- 2-5.精巣がん治療の合併症と副作用
- 2-6.精巣がんの治療終了後の経過観察
- 2-7.精巣がんの患者さんがよく気にしたり悩んだりすることQ&A
- 1.精巣がんとは前のページ »
- 3.精巣がんに関する記事一覧/先進医療/医療機関情報次のページ »
2-1.精巣がんの治療方針
- 精巣がんの治療では、まず精巣を摘出する手術が行われる。
- セミノーマと非セミノーマで治療方針に違いがある。
- Ⅱ期以降の治療では化学療法が中心となる。
精巣がんの治療では、まず精巣を取り除く「高位精巣摘除術」という手術が行われます。精巣腫瘍は進行が速いので、なるべく早く手術を行う必要があります。取り出した精巣の腫瘍に対しては、組織を顕微鏡で調べる病理検査が行われます。
病理検査によって、セミノーマか非セミノーマかが明らかになります。また、転移の有無、転移の起きている部位、転移の大きさや個数などが明らかになることで、病期が決定します。それによって、治療方針が決まってきます。
セミノーマでⅠ期の場合には、①経過観察、②放射線療法、③化学療法という3つの選択肢があります。①は、特に治療は行わず、腫瘍マーカーのLDHで経過を見ていきます。②は、傍大動脈領域に20~25グレイの予防照射を行います。③は、抗がん剤のカルボプラチン単剤で、1~2コースの治療を行います。
非セミノーマでⅠ期の場合には、経過観察か化学療法が行われます。化学療法はBEP療法(詳しくは「精巣がんの治療法2 化学療法」を参照)を2コースです。非セミノーマには放射線が効かないため、放射線療法は選択肢に入っていません。
セミノーマでⅡ期以上の場合には、放射線療法が行われることもありますが、中心となるのは導入化学療法(他の治療に先行して化学療法を行う)です。BEP療法が3~4コース行われます。
非セミノーマでⅡ期以上の場合には、やはり導入化学療法として、BEP療法が3~4コース行われます。
導入化学療法で腫瘍マーカーが正常化したら、後腹膜リンパ節を切除する手術が行われます。後腹膜リンパ節郭清術(かくせいじゅつ)(詳しくは「精巣がんの治療法1 手術」を参照)といいます。切除したリンパ節を調べ、がん細胞が生きていなければ、そこで治療は終わりとなります。生きたがん細胞が存在した場合、セミノーマなら救済化学療法(治療の効果が得られない場合、あるいは再発・再燃した場合に用いる治療)を追加するか、化学療法と放射線療法を加えます。非セミノーマの場合には救済化学療法が行われます。
以上のような治療を行うことで、5年生存率と10年生存率は、Ⅰ期とⅡ期ならどちらも100%、Ⅲ期ではどちらも61%という成績が得られています(杏林大学医学部付属病院のデータ)。
(図)「精巣がんの治療方針」
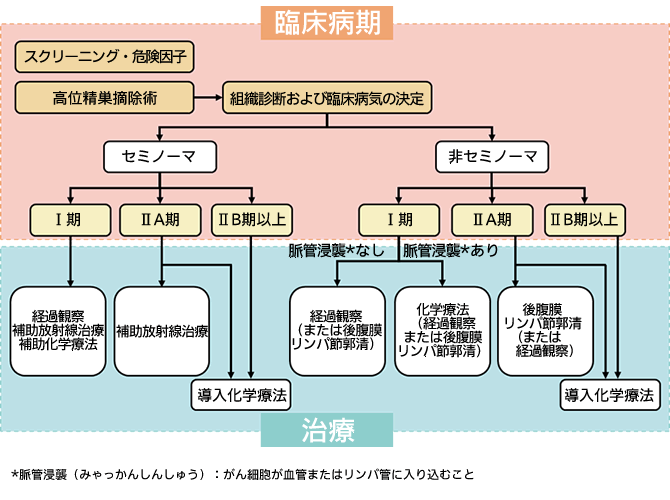
日本泌尿器科学会編「精巣腫瘍診療ガイドライン2009年度」(金原出版)より作成
2-2.精巣がんの治療法――1.手術
- 精巣を摘出する手術はすべての患者さんに行われる。
- Ⅱ期以上の場合は後腹膜リンパ節を切除する手術も行われる。
精巣がんの治療では、次のような手術が行われます。
高位精巣摘除術
精巣がんの治療では、基本的にすべての患者さんに対して行われる手術です。鼠蹊部(そけいぶ)※を切開し、精巣と精索(せいさく)※を併せて切除します。精索は腹腔内につながっているので、できるだけ高位(腹腔に近い高い部分)で切除します。
※鼠蹊部:左右の太ももの付け根の部分
※精索:精子が通る精管と血管が束になっている部分
後腹膜リンパ節郭清術(かくせいじゅつ)
腹部の大きな血管の周囲にある後腹膜リンパ節を切除する手術です。この部分に転移が起きているⅡ期以上の場合は、化学療法を行って腫瘍マーカーの値が正常になってから行われます。切除したリンパ節に生きたがん細胞がいるかどうかで、その後に化学療法や放射線療法を行うかどうかを判断します。Ⅰ期のセミノーマの治療では、再発を予防するために、この手術が行われることがあります。開腹手術が標準的な治療法です。
(図)「高位精巣摘除術」
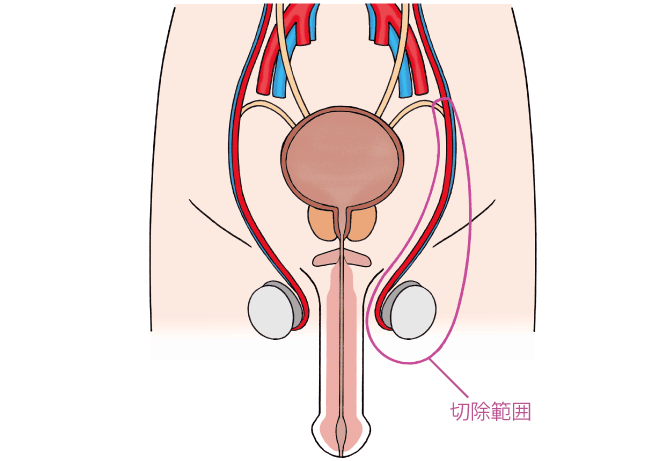
2-3.精巣がんの治療法――2.化学療法
- Ⅰ期のセミノーマでは、カルボプラチン単剤療法が行われることがある。
- Ⅱ期以降のセミノーマの導入化学療法や、非セミノーマのⅠ期の化学療法では、BEP療法が行われる。
- 導入化学療法で十分な結果が得られなかった場合には、2次治療として救済化学療法では、TIP療法が行われる。
Ⅰ期のセミノーマでは、再発を予防する目的で、カルボプラチン単剤療法が行われることがあります。
Ⅱ期以降の導入化学療法(他の治療に先行して化学療法を行う)や、非セミノーマのⅠ期の化学療法では、BEP療法が行われます。ブレオマイシン、エトポシド、シスプラチンを併用する治療法です。
導入化学療法で十分な結果が得られなかった場合には、2次治療として救済化学療法(治療の効果が得られない場合、あるいは再発・再燃した場合に用いる治療)が行われます。かつてはVIP療法(エトポシド、イホスファミド、シスプラチン併用療法)が行われていましたが、治療成績は十分なものではありませんでした。現在は、TIP療法(パクリタキセル、イホスファミド、シスプラチン併用療法)が行われるようになり、治療成績が向上しています。VIP療法の完全寛解率(がんが消失する割合)は25%程度でしたが、TIP療法では70%程度と言われています。1次治療が効かなかった場合でも、2次治療で高い治療成績が得られるようになっているのです。
2-4.精巣がんの治療で使われる薬剤
精巣がんの治療では、次のような抗がん剤が使われています。
(表)「精巣がんの治療で使用する主な抗がん剤」
| 治療法 | 使用される薬剤 一般名(商品名) |
| BEP療法 | ブレオマイシン(ブレオ) エトポシド(ベプシド、ラステッド) シスプラチン(ブリプラチン、ランダ) |
| TIP療法 | パクリタキセル(タキソール) イホスファミド(イホマイド) シスプラチン(ブリプラチン、ランダ) |
| カルボプラチン単剤療法 | カルボプラチン(パラプラチン) |
2-5.精巣がん治療の合併症と副作用
- 後腹膜リンパ節郭清術で射精障害が起きることがある。
- 使用する抗がん剤に応じた適切な副作用対策が必要。
手術によって起こる合併症
後腹膜リンパ節郭清術では、切除する範囲によっては、射精に関わる神経が切断され、逆行性射精という射精障害が起きることがあります。射精したときの感覚はあるのですが、精液が逆行して膀胱内に出てしまうのです。この合併症を防ぐために、神経温存手術も行われています。
化学療法によって起こる副作用
精巣がんの治療で使われる抗がん剤には、次のような副作用があります。
(表)「精巣がんの治療で使用する抗がん剤の主な副作用」
| 薬品名 | 主な副作用 |
| ブレオマイシン | 肺機能障害。肺線維症が起きると、治療を継続できなくなる。 |
| エトポシド | 骨髄抑制、脱毛。 |
| シスプラチン | 吐き気・嘔吐、腎機能障害。吐き気・嘔吐には制吐剤で対応する。腎機能を守るため、十分な補液(点滴による水分補給)が必要となる。 |
| パクリタキセル | 骨髄抑制、脱毛。 |
| イホスファミド | 骨髄抑制、吐き気・嘔吐、脱毛。 |
| カルボプラチン | 骨髄抑制、吐き気・嘔吐。 |
2-6.精巣がんの治療終了後の経過観察
治療が終了しても、再発の有無を確認するために通院する必要があります。通院の頻度は医療機関によってさまざまです。杏林大学医学部付属病院では、治療終了後1年間は、2~3ヵ月に1回は腫瘍マーカー検査を行います。その後は4~6ヵ月に1回のインターバルで腫瘍マーカー検査を行います。CT検査や骨シンチグラフィー検査は必要に応じてですが、少なくとも6ヵ月に1回はCT検査、1年に1回は骨シンチグラフィー検査を行い、これを治療後5年まで続けます。5年間再発がなければ、1年に1回、腫瘍マーカー検査を行います。精巣がんは再発することがあるので、きちんと通院することが大切です。
2-7.精巣がんの患者さんがよく気にしたり悩んだりすることQ&A
- Qセカンドオピニオンは、すべき?
- A
- 担当医の意見が第一の意見であるのに対し、他の医師の意見をセカンドオピニオンと呼びます。すべての患者さんがセカンドオピニオンを聞きに行ったほうがよいわけではありません。担当医の説明を聞き、自分で納得できればそれで十分である場合も多いでしょう。しかし納得がいかない場合には、これまでの治療経過・検査結果・今後の予定などを担当医に記載してもらい、別の医師の意見を聞くのもよいでしょう。そして、その結果を担当医に持ち帰って相談するのがベストです。
- Q手術による射精障害を回避する方法はありませんか?
- A
- 後腹膜リンパ節郭清術(かくせいじゅつ)の合併症として、逆行性射精※が起こることがあります。それを防ぐために神経温存手術が行われていますが、特に神経温存効果が高いのが腹腔鏡下で行う手術です。健康保険が適用されない手術法ですが、先進医療として行われています(正式名称は「泌尿生殖器腫瘍後腹膜リンパ節転移に対する腹腔鏡下リンパ節郭清術」)。腹部に5ヵ所ほど小さな穴を開け、後腹膜腔を気体で膨らませて手術を行います。腹腔鏡で患部を拡大して見ながら手術を行えるため、確実に神経を温存できます。傷が小さいため、手術後の回復が早いのもこの手術の特徴です。
※逆行性射精:射精時に精液が膀胱に流れてしまうこと
- Q治療の影響で精子ができなくなる心配はありませんか?
- A
- 手術で片方の精巣を摘出しても、残った1つの精巣で、十分な精子を作り出すことができます。精子の数は多少減りますが、妊孕性(にんようせい)※には問題ありません。ただ、抗がん剤による治療を受けることで、精子を作る機能が障害されることはあります。化学療法を受けた後、2年間は正常な精子ができなくなるとも言われます。この機能障害は、基本的には回復しますが、心配な場合には精子を凍結保存することもできます。治療を受ける前に、担当医に相談してみるとよいでしょう。
※妊孕性:妊娠出産する能力