第24回 がんの放射線治療の副作用とその対策
~がん種別の最新の放射線治療と副作用 その⑬ 悪性リンパ腫・骨髄腫・白血病~
放射線が持ち合わせる電離作用を駆使して悪性腫瘍を制御する放射線治療は、同時に正常細胞にもダメージを与え、さまざまな有害反応(副作用)を引き起こすことがあります。それでも、現在の放射線治療では、がん病巣への的確な照射が可能になり、放射線障害が確実に減少しています。したがって、放射線治療を始める前から、必要以上にその副作用を心配する必要はありません。
しかしながら、放射線治療についての正しい知識を持ち合わせ、治療後に発症する重い副作用を認識しておかなければ、大事な症状を見逃してしまいがちです。定期的な診察で早期発見に努めるとともに、いざというときの対処法を心得ておくことが、放射線治療を受けるうえでの得策だと言えます。
そのような趣旨で連載している24回目は、「がん種別の放射線治療と副作用」として、悪性リンパ腫・骨髄腫・白血病を取り上げます。ぜひ、副作用対策にも役立てていただきたいと思います。
頭部照射では頭痛・吐き気・耳痛、頸部照射では味覚障害・口内炎に注意
今回、着目した3つのがん種のなかで、最初に悪性リンパ腫について述べます。
悪性リンパ腫は、体内を巡っているリンパ球が異常に増えることで、頸部や腋の下のリンパ節が腫れたり、体の一部にしこりができたりします。病名に「悪性」と冠されていますが、高い確率で治癒を目指すことができます。ただし、悪性リンパ腫は細かく病型は分かれていて、症状や治療効果はさまざまです。
悪性リンパ腫は、ホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫に大別できます。いずれも、放射線治療が奏効しやすいがんの一つとして知られています。
ホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫のいずれも、放射線治療が大きな役割を果たしています。
ホジキンリンパ腫の場合はまず化学療法(ABVD療法:ドキソルビシン、ブレオマイシン、ビンブラスチン、ダカルバジンの4種類の抗がん剤)で縮小を図り、限局期の場合には、残存病変に20~30Gyを照射します。進行期の場合には残存病変が認められる場合に30Gy程度を照射します。
非ホジキンリンパ腫の場合、いくつかの種類がありますが、そのなかでも濾胞性リンパ腫と瀰漫性大細胞型リンパ腫の頻度が高いです。
濾胞性リンパ腫では限局期の場合には放射線治療を30~36Gyを照射します。進行期の場合にはリツキシマブに化学療法(CHOP:シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン)を追加して治療を行います。
瀰漫性大細胞型リンパ腫に関しては、限局期に対しては、10㎝を超える大きな腫瘤がない場合にはR–CHOP3コースに放射線治療40Gy程度か、R–CHOP6~8コースを行います。10㎝を超える大きな腫瘤がある場合には、R–CHOP6~8コースを行い、その後治癒を目指して50Gy程度までの放射線治療を行います。
進行期に対しては、R–CHOP6~8コースを行い、残存病変が認められる場合、もしくは病変が完全に消えても巨大な腫瘤があった場合には50Gy程度までの放射線治療を追加することもあります。
その他、特殊な型の悪性リンパ腫としては粘膜に関連したリンパ組織から発生するMALTリンパ腫と呼ばれる悪性リンパ腫もあります。MALTリンパ腫は主に胃にできることが多く、原因の一つとしてピロリ菌の感染が関係していると考えられ、まず抗生物質で除菌を行います。それだけの治療で治ることもあり、除菌により腫瘍が消えない場合に30Gy程度の放射線治療で治します。その線量で消失する割合はほぼ100%です。
悪性リンパ腫に対する副作用は、照射部位によって異なります。早い時期に起こるものとしては、頭部に照射した場合には、頭重感や吐き気などが、頸部に照射した場合には、味覚障害や口内炎などが挙げられます。
また、胸部では、咳・痰の増加や嚥下障害、発熱など、腹部や骨盤部では、下痢や腹痛、食欲不振などが起きることがあります。
放射線治療に化学療法を併用した場合には、骨髄抑制や肺炎が起こりやすくなるので、注意が必要です。
悪性リンパ腫の場合、照射する線量が比較的少ないので、晩期の有害事象は少ないのですが、どうしても化学療法と併用するため、2次がんの発生がある程度の割合で起こります。
部位に応じた副作用に注意する
骨髄腫は、血液を造る骨髄の中の形質細胞ががん化した病気で、全身に発生する多発性骨髄腫、単発性の孤立性形質細胞腫、血液中に腫瘍細胞ができる形質細胞性白血病の3つがあります。
多発性骨髄腫の治療は、メルファランやシクロホスファミドなどの化学療法が中心になります。放射線治療は、稀に根治を目的とした骨髄移植の前処置として全身照射が行われることもあります。しかし、その大部分は、がん性疼痛の緩和や骨折予防などを目的とした緩和的照射に利用されます。
孤立性形質細胞腫は、放射線治療が比較的よく効き、高い局所制御率が得られるため、根治を目的とした放射線治療が行われます。
骨髄腫に対する放射線治療は、目的に応じて照射範囲や線量が設定されます。
一般に多発性骨髄腫では痛みを除くなど、緩和目的で用いられるため、線量は20~30Gyを10分割程度照射します。
一方、孤立性形質細胞腫は根治を目的とするため、45~50Gyを25回に分割して照射するのが標準的です。
骨髄腫に対する放射線治療の疼痛除去の目的では、痛みが完全に消える確率が20~60%、ある程度改善する確率が60~90%とされています。
加えて、骨折予防のための照射では、45Gy以上の照射をすれば、多くの人で、局所制御が可能です。
骨髄腫に対する放射線治療の主な副作用は、照射部位が人によって異なるので、部位に応じた副作用に注意しなければなりません。
全身照射の副作用は放射線肺臓炎(間質性肺炎)に注意
白血病は「血液のがん」と称される血液疾患で、がん化した造血細胞が骨髄で自律的に増殖して正常な造血を阻害し、多くは骨髄のみに留まらず、末梢血液中にも造血細胞が溢れ出てきます。また、急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、慢性リンパ性白血病などに大別されています。
白血病に対する放射線治療は、骨髄移植の前処置として行われる全身照射が大部分です。全身照射はいずれの白血病も対象となり、シクロホスファミドなどの抗がん剤と併用されます。
主な全身照射の目的は、白血病細胞の死滅と、患者さんのリンパ球の不活性化による拒絶反応の抑制の2つです。抗がん剤治療だけでそれらを行うこともあります。しかし、放射線治療には、大部分の抗がん剤と交叉耐性がないこと、全身のどの部位でも対象となること、危険臓器を避けて照射できることなど、抗がん剤治療にはない特徴があります。
白血病に対する放射線治療では、リニアック(放射線治療装置)の最大照射範囲は、通常、40㎝四方しかなく、いっぺんに全身を照射するには何らかの工夫が必要になります。そのため、
- ①放射線ビームを水平方向から出す(長SAD法)
- ②照射装置を回転させる
- ③治療用ベッドを移動させる
などの方法がとられています。
①の方法は、照射装置と患者さんとの間に十分な距離をとる必要がありますが、十分な広さの治療室さえあれば、他に装置が必要ないため、最も多く用いられています。
照射法は、①の場合、仰向けの姿勢で左右から2門照射、または立位で前後から2門照射を行います。
②と③は、前方1門、または前後対向2門照射が行われます。
白血病に対する放射線の照射は、以前、1回照射が中心でしたが、現在では、総線量12Gyを1回2Gyで、1日2回照射するのが通常です。
白血病に対する放射線治療の主な副作用は、骨髄移植自体で起こる副作用にマスクされますが、急性期には放射線肺臓炎(間質性肺炎)が、晩期としては白内障や腎障害が、それぞれ代表的なものです。また化学療法と併用しているので、2次がんの発生も挙げられます。間質性肺炎に備えて肺への線量を低く抑えることも重要です。
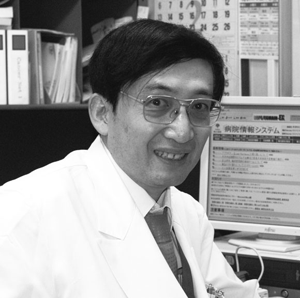
唐澤 克之(からさわ・かつゆき)
1959年東京生まれ。東京大学医学部卒業後。1986年スイス国立核物理研究所客員研究員。1989年東京大学医学部放射線医学教室助手。1993年社会保険中央総合病院放射線科医長。1994年東京都立駒込病院放射線科医長となり、2005年より現職。専門は放射線腫瘍学。特に呼吸器がん、消化器がん、泌尿器がん。日本放射線腫瘍学会理事、日本頭頸部腫瘍学会評議員、日本ハイパーサーミア学会評議員。近著に『がんの放射線治療がよくわかる本』(主婦と生活社)などがある。








