第10回 がんの放射線治療の副作用とその対策
~手術・化学療法にはない放射線治療のメリット~
放射線が持ち合わせる電離作用を駆使して悪性腫瘍を制御する放射線治療は、同時に正常細胞にもダメージを与え、さまざまな有害反応(副作用)を引き起こすことがあります。それでも、現在の放射線治療では、がん病巣への的確な照射が可能になり、放射線障害が確実に減少しています。したがって、放射線治療を始める前から、必要以上にその副作用を心配する必要はありません。
しかしながら、放射線治療についての正しい知識を持ち合わせ、治療後に発症する重い副作用を認識しておかなければ、大事な症状を見逃してしまいがちです。定期的な診察で早期発見に努めるとともに、いざというときの対処法を心得ておくことが、放射線治療を受けるうえでの得策だと言えます。
そのような趣旨で連載している10回目は、手術・抗がん剤にはない放射線治療のメリットについてお話させていただきます。ぜひ、副作用対策にも役立てていただきたいと思います。
放射線治療は可能性を秘めている
放射線治療は手術・化学療法と並ぶがん治療の3本柱でありながら、海外の医療先進国と比べて日本では受ける人の割合が少ないようです。近年の照射技術の進歩に伴い、一昔前より増えているとはいえ、がん患者さん全体の約25%にすぎません。それに対し、アメリカが66%、ドイツが60%、イギリスが56%というデータがあるくらい、これらの国々のがん患者さんは、日本より高い割合で放射線治療を受けているのです。
日本において放射線治療の普及が遅れた理由として、いくつかの要因が考えられます。その1つは、日本のがん医療が長期にわたり、手術を中心として成り立ってきたことです。たとえば、日本では胃がんのように手術が適したがんが多くを占めていたため、病巣を切除することが最良の治療であるといった固定観念ができてしまっていたのでしょう。
2つ目の理由としては、放射線治療自体には、現在のような精密な照射技術がなかったために重い副作用を引き起こしやすく、治療法として十分に発展していなかった点が挙げられます。
しかし、現在、手術で切除してもしなくても生存率が変わらないがんもあることがわかってきています。ですから、検査などでがんのタイプをよく見極め、的確な治療法の選択が行われるようになっています。
その1つの大きな選択肢となっている放射線治療は、がんのある場所を対象に治療を行う局所療法です。白血病などの血液のがんでは全身に照射することもありますが、それは特殊なケースといっていいでしょう。
抗がん剤治療は、薬剤の成分が血管を通って全身に運ばれ、いろいろな臓器に影響を及ぼします。そのため、たとえば大腸がんの治療薬で胸痛や口内炎など、治療部位から離れた場所に副作用が現れることが珍しくありません。それに対し、放射線治療の副作用は正常細胞が放射線によって傷つくために起こるので、治療部位以外に副作用が起こりません。
さらに、放射線治療の場合、定位放射線治療など最新のピンポイント照射により、正常な組織への照射を大幅に減らすことができます。しかも、このような照射技術は、今後も進歩し続ける可能性を秘めているのです。かといって、放射線治療の副作用がなくなるというわけではありません。それでも、適切な治療計画を立てて照射すれば、回復不能な副作用が現れることはほとんどありません。現在の放射線治療で起こる副作用の大部分は、治療後1~2カ月すれば自然に治るものです。
手術と放射線治療の治療成績はほぼ同等
同じ局所療法である手術と比較しても、放射線治療にはいくつかのメリットがあります。なかでも最大のメリットは「切らずに治せる」ということです。
少し前の日本では、手術でがんを切除してしまうのが最も確実な治療法とされてきました。たしかに、部位によってはそのようながん種があります。しかし、近年、がんによっては、病巣部をすべて切除しても再発するケースがあることがわかってきました。手術が確実な治療法とは限らないのです。
また、臓器を摘出すれば何らかの後遺症が、生涯にわたって残ることになります。その点、同じ局所療法でも、放射線治療の場合は臓器がそのまま残存するので、術前とそれほど変わらない生活を送ることができます。さらに、体にメスを入れずにすむので、治療そのものには痛みがなく、一部の特殊な治療法を除けば麻酔も不必要です。
従来の放射線治療は、手術で切除し切れないがんへの補助的治療として用いられるケースが大半でした。このことが、放射線治療の効果が低く見られてきた理由の1つになっています。
一般的に、放射線治療にしても、手術にしても言えるのは、病巣が小さければ小さいほど治療成績が向上するということです。切除すれば根治が見込めるがんを対象とする手術と、手術で切除できないがんを対象とする放射線治療を単純に比べると、放射線治療の治療成績が劣るのは、ある意味で当然の結果なのです。
近年になって、EBM(科学的根拠に基づいた医療)が重視され、多くの症例を基にその治療法が有効か否かを科学的に評価するようになりました。そして、病期などを同じくした条件で調べた結果、多くのがんにおいて放射線治療が手術に匹敵する高い効果を発揮することがわかってきました。例を挙げると、喉頭がんのなかでも声門にできた早期のものであれば、5年生存率は90%以上という成績をあげています。この数字は手術と比較して遜色のないもので、声帯を失う危険性もありません。
肺がんにおいても、多数の施設が行った早期のものに対する定位放射線治療では、5年生存率は約70%でした。この数字は、手術の標準的な治療成績と同等です。
また、放射線治療の治療期間は、一般的に分割照射が行われるので、1~2カ月ほどの期間が必要になります。しかし、1回の治療にかかる時間は驚くほど短く、1つの部位に対する照射であれば、約10分で終わります。しかも、そのうちの半分くらいは体の位置決めなどに費やされ、実際に放射線が照射されるのは5分ほどで、ときには数秒で照射が終わることもあります。
そのように、1回の治療時間が短いことや、副作用が少なく治療後の体調管理が手術や抗がん剤よりも楽なことから、放射線治療は外来通院で受けることが可能なのです(小線源治療などを除く)。
がん治療のあらゆる場面で貴重な役割を果たす
医学は日進月歩。昨今は、がんの複雑な発症メカニズムが徐々に明らかになるにつれ、がんの種類や進行度などに応じ、最適な治療法の組み合わせの必要性が認識されてきました。この治療戦略は「集学的治療」と呼ばれ、手術や抗がん剤治療・放射線治療などを併用する治療法が注目を浴びてきているのです。こうした集学的治療を行う際、放射線治療の「身体的負担の少なさ」や「治療時間の短さ」などのいくつかの長所が大きなメリットになります。
放射線治療を目的別に分ければ、根治的照射、予防的照射、手術または化学療法との併用療法、緩和的照射に分類できます。これは、放射線治療ががん治療のあらゆる場面で貴重な役割を果たしている証左でもあります。
根治的照射とは、完全な治癒を目的とした放射線治療です。元々、放射線治療は基本的に手術と同じ局所療法なので、根治的照射の対象となるがんは、遠隔転移がない病期までとなります。
根治の可能性は、がんが小さければ小さいほど高くなります。そして、病巣が小さければ、正常組織への照射量も少なくなり、副作用のリスクが減少します。そのため、がんに十分な線量を集中させることが可能になるのです。
放射線治療で根治が期待できるがん種は多く、主なものとしては肺がんや前立腺がんのほか、喉頭がんや咽頭がんといった頭頸部がん、子宮頚がん、食道がん、悪性リンパ腫などが挙げられます。実際、これらのがん種では、手術に匹敵する治療成績をあげているものも多く、なかでも前立腺がんに対する強度変調放射線治療(IMRT)や密封小線源治療が良好な成績をあげ、多くの人の耳目を集めています。また、喉頭がんでも、優れた治療成績が収められています。
ただし、遠隔転移がなくてもがんが大きく成長している場合には、正常組織への線量が増えすぎてしまいます。そのため、放射線治療単独では根治が困難になります。その場合には、抗がん剤で病巣を縮小させてから放射線治療を行う化学放射線療法で根治を目指します。
放射線治療と手術の併用は、がんの治療ではしばしば行われます。その場合、術前照射、術中照射、術後照射の3ケースがあります。
術前照射は、がんが大きすぎて切除できない場合に、切除可能な大きさにまでがんを縮小させることを目的として行われます。また、切除ができる大きさのがんでも、事前にがんを縮小しておくことで切除範囲を狭くし、患者さんの体への負担や後遺症を軽減させるメリットもあります。あるいは、手術部位の周辺に画像ではわからない微小ながんが潜んでいる場合に備え、事前に放射線治療で死滅させておくという目的もあります。
術中照射は、手術で病巣を切除した後に引き続き、肉眼では捉えることができない微小ながんが残るのを防ぐのを目的に、切除部位に放射線を照射する方法です。開腹した状態で周囲の臓器を手で移動させ、肉眼で位置を確認しながら放射線を照射します。そのため、周辺の正常組織への影響が最小限で抑えられ、副作用のリスクが大幅に減少します。また、大きな線量を照射できるので、高い効果が期待できます。一般的には、通常の分割照射1回あたりの約10倍という線量が照射されます。
術後照射は予防的照射とも呼ばれ、一般的に手術でがんを切除した後に、取り切れなかった微小ながんによる再発を予防する目的で行われます。たとえば、乳がんに対する乳房温存療法は放射線で再発の予防をするので切除範囲を抑えることが可能になります。この予防的照射は、乳がんのほか、子宮頸がん、肺がん、骨軟部腫瘍などに対してよく行われています。
術後照射のもう1つの使われ方として、手術では切除できない部位にがんが広がっている場合に、切除可能な部位だけを切除しておき、残存部分を照射して死滅させるというものがあります。また、通常の放射線治療とは異なり、がんが大きすぎて放射線治療で根治が期待できない場合、手術でがんを小さくしてから放射線治療で根治を目指すこともあります。
このように、身体的負担が少ない、治療時間が短いといったいろいろな特長を持った放射線治療は、がん治療のさまざまなケースで活躍しているのです。
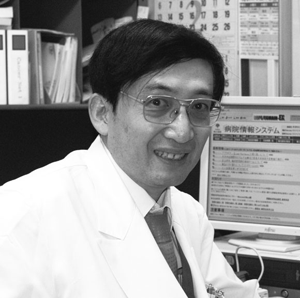
唐澤 克之(からさわ・かつゆき)
1959年東京生まれ。東京大学医学部卒業後。1986年スイス国立核物理研究所客員研究員。1989年東京大学医学部放射線医学教室助手。1993年社会保険中央総合病院放射線科医長。1994年東京都立駒込病院放射線科医長となり、2005年より現職。専門は放射線腫瘍学。特に呼吸器がん、消化器がん、泌尿器がん。日本放射線腫瘍学会理事、日本頭頸部腫瘍学会評議員、日本ハイパーサーミア学会評議員。近著に『がんの放射線治療がよくわかる本』(主婦と生活社)などがある。










