第33回 がんの放射線治療の副作用とその対策
~主な適応と照射範囲の設定法 その⑦ 膵がん~
放射線が持ち合わせる電離作用を駆使して悪性腫瘍を制御する放射線治療は、同時に正常細胞にもダメージを与え、さまざまな有害反応(副作用)を引き起こすことがあります。それでも、現在の放射線治療では、がん病巣への的確な照射が可能になり、放射線障害が確実に減少しています。したがって、放射線治療を始める前から、必要以上にその副作用を心配する必要はありません。
しかしながら、放射線治療についての正しい知識を持ち合わせ、治療後に発症する重い副作用を認識しておかなければ、大事な症状を見逃してしまいがちです。定期的な診察で早期発見に努めるとともに、いざというときの対処法を心得ておくことが、放射線治療を受けるうえでの得策だと言えます。
そのような趣旨で連載している33回目は、難治性がんの代表格とされる膵がんを取り上げ、その特徴と治療方法について最新の知見を交えて概説します。ぜひ、副作用対策にも役立てていただきたいと思います。
発見時には進行しているケースが多い難治性の代表格
ヒトの膵臓は成人では15㎝ほどの大きさで、くさび型をしています。右端は、肝臓の下にある十二指腸がコの字型に曲がった部分の間にはまり込む位置にあります。左端は、腹部の左側に位置する脾臓のあたりまで達しています。その部位によって、膵頭部(右側)・膵体部・膵尾部(中程から左側)に分けられています。
その膵臓にできる悪性腫瘍、つまり膵がんは比較的男性に多く、年齢別では60歳前後から増加して高齢者ほど高い傾向にあります。また、膵がんは浸潤・転移しやすいことで知られています。浸潤は膵周囲後腹膜のほか、腹膜や胃、脾臓、門脈、神経などに達しやすく、転移はリンパ節をはじめ肝臓や腹膜、肺、骨、腎、副腎、骨などに見られます。
一般に、膵がんは通常の健康診断で発見されることはほとんどありません。腹痛・背部痛・腰痛・食欲不振・体重減少・黄疸といった自覚症状を覚えて医療機関を受診し、臨床検査や画像診断などによって発見されます。そのときにはすでに周辺臓器に浸潤・転移していることが少なくありません。この場合、すべてのがんを摘出することが困難と判断され、手術が不可能な状況に陥ってしまいます。
また、膵がんは他のがん種と比べ、KRAS,CDKN2A/p16,TP53, SMAD4/DPC4といった4つの遺伝子異常のみが高頻度に認められています。昨今、これらの遺伝子が膵がんの発生に強く関与していることが究明されているのです。
発見されにくい・予後不良・局所および肝転移などへの進展が早期に起こりやすい膵がんは、難治性がんの代表格です。このがん種に対する化学療法や放射線治療の感受性が乏しいとされ、切除ができたケースでも長径が1㎝を超えると予後が悪くなるとされています。
術前化学療法と併用しての放射線治療終了後6週間程度で手術を行うのが一般的に
現在、膵臓がんで根治が期待できる治療法は手術だけだと言われています。放射線治療が選択されるのは手術不能な場合で、最近では化学療法と併用する化学放射線療法として行われるケースが増えています。ただし、手術可能な割合は膵がん全体の10~20%と、決して高い割合ではありません。しかも、その大部分は切除不能な局所進行がんが占めています。ですから、放射線治療が果たす役割は重要だと言えます。
それでも、膵がんの治療の主体となるのは外科的切除(手術)です。しかしながら、切除可能である膵がんの割合は高くなく、また切除可能な膵がんであっても、術前治療を行わずに切除を行うと、遠隔転移や局所再発を来すことも少なくありません。そのようなことから、依然として標準治療は術前治療を行わずに切除(手術)とされていますが、最近では徐々に術前治療が行われるようになりつつあり、治療成績が改善したという報告も出だしています。
その理由として考えられることは、膵がん腫瘤の周囲にはすでに顕微鏡的な浸潤が存在しており、腫瘤のみを切除してもその周囲に浸潤したがん細胞が残存し、それらが時間をおいて、肝臓や腹膜に転移を来したり、局所で増殖したりして、再発するということが指摘されています。
もちろん、放射線療法は主たる腫瘍を縮小し、あわよくば消失させることも稀に期待できます。けれども、主な目的は腫瘤の周囲にある腫瘍細胞の浸潤を制御することにより、手術により腫瘤を切除した後の再発を抑制することです。
以前は腫瘍切除を行った後に術中もしくは術後に放射線治療を行っていましたが、前述したような理由から肝臓や腹膜に転移を来すことが多く見受けられ、大半の患者さんのことを救えていませんでした。現在では術前に化学療法と併用して放射線治療を50Gy程度投与し、効果が最大になる放射線治療終了後6週間程度で手術を行うことが通常となってきています。
抗がん剤・放射線・手術を上手に組み合わせれば、治療成績は絶望的ではなくなってきた
膵がんに対する放射線療法は、昔から困難とされてきました。それは膵がんの放射線感受性があまり高くないこと、膵臓が沈黙の臓器であるため、発見されたときにはすでにかなりの大きさになっており、根治させるには多くの線量が必要である一方で、胃や十二指腸、肝臓、腎臓、脊髄などの放射線感受性の高い臓器に取り囲まれているため、線量の投与が困難であることなどがその理由です。そのため、過去には手術を行う際に、膵臓を露出して、胃や腸管などの臓器を照射野から外して、膵がんのみに1回大線量を投与するという術中照射という技法を用いて、治療の強度を上げるような治療も行われていました。しかし、現在ではほとんど行われなくなってきました。
現在ではできるだけ狭い範囲に高い線量を確実に投与することができる高精度放射線治療という方法が普及してきています。その一つの方法が、照射野の中の線量強度を変え、最適な線量の分布を取らせる強度変調放射線治療という方法が膵がんにも応用されるようになってきています。
従来の3次元原体照射法と強度変調放射線治療との線量分布の違いを図1に示します。強度変調放射線治療のほうが周囲の正常臓器への線量が低減されていることがわかります。
膵がんの放射線治療での有害事象としては、腫瘍に接している胃や十二指腸に対するものが最も懸念され、急性期には食思不振、悪心、嘔吐などが認められます。また胃や十二指腸への晩期有害事象としては、同部位の潰瘍および出血などが挙げられます。当院でも胃や十二指腸への合併症を減らすべく、強度変調放射線治療の技法を用いて治療を行っています。腎臓に関しては、比較的線量低減は可能で、耐容線量を超えることは稀ですが、術後も長期に続ける抗がん剤治療による影響も考慮し、可及的に低い線量に抑えることが肝要です。また、肝臓、脊髄への線量も強度変調放射線治療を用いることにより、臨床的に問題にならないレベルまで減らすことが可能です。
放射線療法は、通常、1回線量2Gyにて行いますが、膵がんの場合、周囲に放射線感受性の高い臓器がたくさんあることと、抗がん剤の同時併用が一般的であるので、一般に1回1・8Gyの線量を28~30回程度照射を行います。
また、数多くの臨床試験の結果から、抗がん剤を併用することが強く推奨されています。抗がん剤は放射線治療と同時に行います。放射線治療の前にも行うことがあります。抗がん剤の併用はもちろん遠隔転移を減らすためにも重要ですが、膵がんの場合、腫瘍局所への放射線療法の効果を高めることがより重要であるため、放射線治療と同時に行うことが重要です。また、術後の補助療法として、手術を行った後にも投与が続けられることが、予後の改善に寄与しています。それと、抗がん剤を同時併用する際には術後の抗がん剤療法をしっかり行うために、患者さんの全身状態との兼ね合いで、あまり強力な化学療法を併用しすぎないことも重要です。当院では同時併用の際に用いる抗がん剤としてはTS–1を使用しています。
治療成績ですが、最近では、化学放射線治療が終了し、治癒切除が行われた症例の長期成績は5年全生存率が40~50%にも到達してきており、うまく抗がん剤、放射線と手術を組み合わせれば、膵がんの治療成績も以前ほど絶望的なものではなくなってきました。
それにつけても早期に発見されることが何よりも重要で、切除可能な症例では、われわれの行っている化学放射線治療により、組織学的完全奏効率が10~20%にまで到達し、そのような症例は切除後も再発なしで長期生存しています。よって予後因子としては、組織学的完全奏効を得ること、並びに手術時に切除断端に腫瘍の露出がないこと(治癒切除)が挙げられます。そのためにはやはり早期発見・早期治療がとても重要です。
最近では、MRIを搭載したリニアックも登場し、放射線治療中に膵臓の位置をMRIでモニターしながら治療することができ、1回の線量を増加させて、定位照射(ピンポイント照射)の形で安全に治療を行うことが可能になり、治療成績が向上している報告も出されています。
膵がんへの有効性が認められている重粒子線治療
一般に、膵がんに放射線治療の効果が乏しいのは、X線が効きにくい腺がんであることが理由の一つに挙げられます。そこで期待されているのが、組織型を問わず効果が期待できる重粒子線による治療です。
重粒子は文字通り電子よりも重い粒子のこと。陽子もその一つですが、一般的に重粒子線治療と言えば炭素イオン線による治療を指します。
重粒子線は体内に入った後、設定された深さまではほとんどエネルギーを放出せずに早い速度で通過する性質を持っています。そして、目的の場所で急に速度を落として膨大なエネルギーを放出し、その後に体内で停止します。
重粒子線治療の陽子線治療との相違は、陽子よりも重い炭素原子核を使用する点。そのため、陽子線治療より大きなエネルギーが必要となる反面、がんに対する治療効果は陽子線治療の約3倍とも言われています。さらに、重粒子線治療はがんの組織型を問わずに高い効果が期待できますし、X線が苦手とする低酸素状態のがん細胞にも大きな効果を発揮します。
膵がんの手術は難易度が高く、日本の外科医のレベルを以てしても、一定の割合で合併症が発生します。それに対し、重粒子線治療は、体にメスを入れないので、手術のような痛みも合併症もありません。体への負担が少ないことに加え、入院する必要もなく、生活や仕事などへの影響も最低限ですみます。
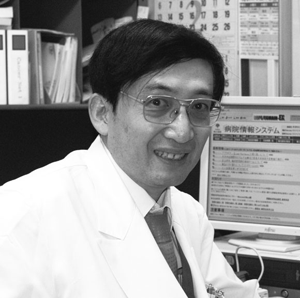
唐澤 克之(からさわ・かつゆき)
1959年東京生まれ。東京大学医学部卒業後。1986年スイス国立核物理研究所客員研究員。1989年東京大学医学部放射線医学教室助手。1993年社会保険中央総合病院放射線科医長。1994年東京都立駒込病院放射線科医長となり、2005年より現職。専門は放射線腫瘍学。特に呼吸器がん、消化器がん、泌尿器がん。日本放射線腫瘍学会理事、日本頭頸部腫瘍学会評議員、日本ハイパーサーミア学会評議員。近著に『がんの放射線治療がよくわかる本』(主婦と生活社)などがある。










