第19回 がんの放射線治療の副作用とその対策
~がん種別の最新の放射線治療と副作用 その⑧ 膀胱がん・精巣がん~
放射線が持ち合わせる電離作用を駆使して悪性腫瘍を制御する放射線治療は、同時に正常細胞にもダメージを与え、さまざまな有害反応(副作用)を引き起こすことがあります。それでも、現在の放射線治療では、がん病巣への的確な照射が可能になり、放射線障害が確実に減少しています。したがって、放射線治療を始める前から、必要以上にその副作用を心配する必要はありません。
しかしながら、放射線治療についての正しい知識を持ち合わせ、治療後に発症する重い副作用を認識しておかなければ、大事な症状を見逃してしまいがちです。定期的な診察で早期発見に努めるとともに、いざというときの対処法を心得ておくことが、放射線治療を受けるうえでの得策だと言えます。
そのような趣旨で連載している19回目は、「がん種別の放射線治療と副作用」として膀胱がん・精巣がんを取り上げます。ぜひ、副作用対策にも役立てていただきたいと思います。
浸潤性の膀胱がんには放射線治療の役割が期待される
今回、着目する2つのがん種の1つである膀胱がんは、泌尿器系では、前立腺がんに次いで多いがん種で、再発を繰り返しやすいのが特徴です。
膀胱がんは、膀胱の尿路上皮(移行上皮)粘膜より発生する悪性腫瘍です。病理組織学的には、その約90%以上は尿路上皮がんです。その他、扁平上皮がんが数%、腺がんが2%弱を占めています。
膀胱がんの臨床的可視病変の完全特徴として、空間的・時間的多発性があげられます。つまり、診断時には、すでに膀胱内腔において多発する場合や、内視鏡下による切除後に膀胱内再発を認める頻度が高いのです。また、膀胱同様に、尿路上皮粘膜を有する腎盂・尿管・前立腺部尿道といった他の尿路に病変を合併することも少なくなく、膀胱がんの診断では、尿路全体をスクリーニングする必要があります。
膀胱の粘膜の下には、3層の平滑筋からなる筋層があります。その筋層を超えて浸潤すると、周囲の脂肪組織を経て、リンパ節転移や遠隔転移を起こしやすくなります。そのため、がんの大きさよりも、筋層にどれだけ深く浸潤しているかによって予後が左右されます。ただ、膀胱がんの4分の3は、浸潤のない表在性がんの段階で発見されます。
表在性の膀胱がんに対しては、内視鏡による経尿道的切除術と抗がん剤、あるいはBCG(フランスで開発されたワクチン)の膀胱内注入の組み合わせが有効な治療法として確立されています。したがって、表在性の膀胱がんには放射線治療が行われることはありません。
その一方で、浸潤性の膀胱がんにおける根治可能な治療法としては、人工膀胱が必要になる膀胱全摘術か、放射線治療の選択肢があります。膀胱全摘術は、80~90%の高い局所制御率をあげています。しかし、5年生存率は約50%とされています。それに対し、放射線治療は、局所制御率が手術に劣るものの、5年生存率は化学療法との併用によって手術と同等の成績があると言われています。加えて、放射線治療の場合は、膀胱を温存できるというメリットがあります。
従来は、浸潤性の膀胱がんの標準的治療は膀胱全摘術でした。しかし、今後は膀胱温存を目指した根治的治療として、放射線治療の役割が大きくなると思われます。
晩期の副作用として直腸出血・慢性膀胱炎・膀胱委縮の可能性も
一般に、膀胱がんの放射線治療の場合、経尿道的切除術でがんを可能な限り切除した後に外部照射を行います。膀胱がんはいっぺんにいくつもできることが多いため、膀胱全体と転移を起こしやすい骨盤リンパ節を含めた範囲に照射します。その後、がんの縮小に合わせ、照射範囲を膀胱だけ、あるいは膀胱の一部に絞ります。
なお、毎回の治療時に照射範囲のズレが生じないようにするため、そして、治療計画時の撮影と同じになるようにするために、排尿のタイミングへの注意が必要です。
膀胱がんに対する放射線治療の線量は、基本的に1回1・8~2Gyの通常分割照射が行われます。ただし、骨盤リンパ節への照射は40~45Gy(4~5週間)までとし、その後は、15~20Gyを膀胱に的を絞って照射します。
骨盤リンパ節を含めた照射では、前後対向2門を加えた4門照射が行われます。左右からの照射については、可能な限り直腸を照射範囲からはずすため、事前にバリウムを注入し、直腸の位置を確認することがあります。そして、がんが縮小した後の膀胱への追加照射は、主に4門照射が選択されます。
また、併用される化学療法としては、M–VAC療法(メソトレキサート、ビンブラスチン、ドキソルビシン、シスプラチン)が多いようです。化学療法は、放射線治療の前よりも、同時に行うほうが効果的だとされています。
浸潤性の膀胱がんに対する放射線治療単独の局所制御率は40~60%で、5年生存率は30~50%と言われています。それに対し、経尿道的切除後の化学放射線療法では、局所制御率は60~80%、5年生存率は50~60%となっています。
膀胱がんに対する放射線治療の主な副作用としては、下痢や頻尿、排尿時痛などが、放射線治療期間の中盤から後半に起こることがあります。また、晩期の副作用としては、直腸出血や慢性膀胱炎、膀胱委縮が起こる可能性があります。
セミノーマと非セミノーマの判別が治療法の大きなポイント
今回、取り上げる2つ目のがん種である精巣がんは、2つの特徴があります。その1つは、他のがん種が中高年に見られることが多いのに対し、精巣がんは25~35歳くらいの比較的若い男性に多いことです。もう1つは、他のがん種が転移をすると根治させることがとても難しくなるのに対し、精巣がんは、転移をしていても適切な治療を行えば根治できるケースが多い病気です。
その精巣がんは、いくつかの種類に大別されます。ただ、一般に精巣がんと言えば「胚細胞腫瘍」を指します。胚細胞腫瘍は、さらに精巣上皮腫(セミノーマ)と非精巣上皮腫(非セミノーマ)に分類されます。放射線治療の対象となるのは主にセミノーマですので、本稿ではセミノーマについて説明します。
セミノーマは、放射線治療が比較的よく効くがんとして知られていますが、抗がん剤も比較的よく効くがん種です。それに対し、非セミノーマは、抗がん剤がよく効くものの、放射線治療はそれほど効果を得られません。そのため、両者の判別は治療法を決めるうえで、とても大切なのです。
セミノーマの病期分類は、Ⅰ期からⅢ期に分類できます。
Ⅰ期は、がんが原発巣に限局している状態です。
Ⅱ期には、ⅡA期とⅡB期があります。ⅡA期は、腹部大動脈または腹部大静脈の周囲に限局した(横隔膜より下の)リンパ節転移があり、転移巣の大きさが5㎝以下の状態です。ⅡB期は、横隔膜より下のリンパ節転移があり、転移巣の大きさが5㎝以上の状態です。
Ⅲ期には、ⅢA期・ⅢB期・ⅢC期があります。ⅢA期は、Ⅱ期以外の横隔膜より上のリンパ節にも転移がある状態です。ⅢB期は、肺に転移している状態です。ⅢC期は、肝臓や脳に転移がある状態です。
放射線治療の対象となるセミノーマは、主にⅠ~Ⅱ期で、手術との併用で術後照射が行われます。
セミノーマに術後照射を行う場合でも、最近は副作用を軽減させるため、骨盤部を除いて腹部傍大動脈リンパ領域だけに照射するのが一般的になっています。
副作用として消化器症状・精子数の減少などが起こる
セミノーマは放射線感受性が高いので、総線量は比較的少量ですみます。Ⅰ期であれば20~25Gyを、Ⅱ期であれば30~36Gyを、1回あたり1・5~2Gyの通常分割照射で治療します。
なお、病期によって治療法の選択肢が少し異なります。
- Ⅰ期:Ⅰ期のセミノーマに対しては、従来は骨盤部と腹部傍大動脈リンパ領域に術後照射(ドッグレッグ照射)を行うのが一般的でした。しかし、Ⅰ期ではリンパ節転移が少ないので、最近では術後の観察を厳重に行うことで再発をチェックし、術後照射を行わない場合もあります。
ただ、術後照射を行えば、再発はほぼ完全に防げるものの、術後照射を省略すると、約10%に再発が起こります。また、再発予防効果は、化学療法も放射線治療と同等とされています。そのため、患者さんは、どの治療法を選択するのかを主治医とよく相談したうえで決めることになります。 - ⅡA期:Ⅰ期の治療より、総線量を5~10Gy追加します。リンパ節転移があっても転移巣が小さい場合には、術後照射で高い治癒率が期待できます。また、術後照射に代わり、化学療法を選択することも可能です。
- ⅡB期以降:放射線が効きやすいセミノーマといえども、がんがある程度大きくなると治療成績が落ちてきます。そのため、放射線治療は化学療法と併用するか、化学療法でがんを小さくしてから手術を行うか、2つの治療法が選択肢となります。手術前にがんを縮小させる補助療法としては、基本的に化学療法を行います。
これらの病期ごとの治療成績ですが、Ⅰ期の治癒率は95%以上ですから、ほとんどの患者さんで治癒が期待できます。また、ⅡA期の治癒率はⅠ期のそれよりもやや落ち、90%前後になります。そして、ⅡB期では80%程度まで低下します。
こうした、セミノーマに対する主な副作用として比較的多く見られるのは、下痢などの消化器症状です。また、放射線治療の前に精巣を摘出していることもあり、骨盤まで照射範囲を広げると精子数の減少が起こることもあります。
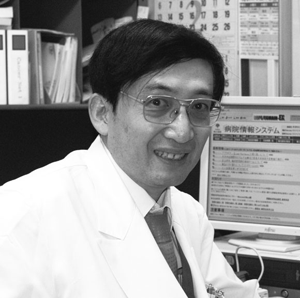
唐澤 克之(からさわ・かつゆき)
1959年東京生まれ。東京大学医学部卒業後。1986年スイス国立核物理研究所客員研究員。1989年東京大学医学部放射線医学教室助手。1993年社会保険中央総合病院放射線科医長。1994年東京都立駒込病院放射線科医長となり、2005年より現職。専門は放射線腫瘍学。特に呼吸器がん、消化器がん、泌尿器がん。日本放射線腫瘍学会理事、日本頭頸部腫瘍学会評議員、日本ハイパーサーミア学会評議員。近著に『がんの放射線治療がよくわかる本』(主婦と生活社)などがある。








