第12回 がんの放射線治療の副作用とその対策
~がん種別の最新の放射線治療と副作用 その① 脳腫瘍~
放射線が持ち合わせる電離作用を駆使して悪性腫瘍を制御する放射線治療は、同時に正常細胞にもダメージを与え、さまざまな有害反応(副作用)を引き起こすことがあります。それでも、現在の放射線治療では、がん病巣への的確な照射が可能になり、放射線障害が確実に減少しています。したがって、放射線治療を始める前から、必要以上にその副作用を心配する必要はありません。
しかしながら、放射線治療についての正しい知識を持ち合わせ、治療後に発症する重い副作用を認識しておかなければ、大事な症状を見逃してしまいがちです。定期的な診察で早期発見に努めるとともに、いざというときの対処法を心得ておくことが、放射線治療を受けるうえでの得策だと言えます。
そのような趣旨で連載している12回目は、がん種別の放射線治療・副作用として脳腫瘍を取り上げます。
ぜひ、副作用対策にも役立てていただきたいと思います。
神経膠腫に対する照射の副作用は中耳炎や頭痛、嘔吐など
脳腫瘍には原発性脳腫瘍と転移性脳腫瘍とがあります。本稿では、原発性脳腫瘍について述べさせていただきます。
原発性脳腫瘍には良性のものもありますが、その多くは悪性です。ただ、良性とはいっても徐々に大きくなってしまい、放置すれば周囲の組織を圧迫して死に至るケースもあります。
原発性脳腫瘍は手術による切除が基本です。しかし、手術で摘出し切れないケースも少なくなく、取り残したがんに対する治療や再発防止のために放射線治療が重要な役割を果たすわけです。
放射線治療は、主に悪性脳腫瘍の全部と良性腫瘍の一部に対して行われます。その多くは手術との併用ですが、単独、あるいは化学療法と併用されることもあります。
脳と脊髄には、神経細胞と神経線維以外に、その間を埋めている神経膠細胞(グリア細胞)があります。その神経膠細胞から発生する脳腫瘍が神経膠腫(グリオーマ)です。
神経膠腫にはさまざまなタイプがあり、悪性度の低いものから順にⅠ~Ⅳの4つのグレードに分けられます。そのうち、グレードⅠとⅡのものを低悪性度神経膠腫と言い、グレードⅢとⅣのものを悪性神経膠腫と称しています。前者には、びまん性星細胞腫・乏突起膠腫などが、後者には、最も悪性度の高い膠芽腫のほか、退形成性星細胞腫や退形成性乏突起膠腫などがあります。
神経膠腫の治療は、病期を問わず、根治的照射が行われます。ただし、事前に手術で可能な限りがんを摘出し、取り切れなかったがんを放射線で治療するのが基本です。
治療の実際としては、6~10MVのX線を用いて、直交2門照射、ウェッジ・フィルターを使った3門照射、4門照射などが行われます。ただ、照射する線量や照射範囲は悪性度によって少し異なります。
悪性神経膠腫への照射方法は、脳全体に放射線をあてる全脳照射と、がんのある場所に限定して照射する局所照射に大別されます。以前は全脳照射が主流でしたが、最近では局所照射が一般的になってきました。
局所照射には、通常の局所照射と、照射範囲を広めにとる拡大局所照射があります。いずれにしても、腫瘍床(手術でがんを切除した部分)と手術で取り切れなかったがんが照射範囲に含まれます。
通常の局所照射では、照射される範囲が腫瘍床や残存腫瘍の周囲2~2・5㎝、またはがんの浸潤によって浮腫が起きている範囲をマージン(余白)として照射範囲に含めます。それに対し、拡大局所照射の場合には、浮腫の範囲に、さらに1・5~2㎝のマージンをとって照射を行います。
照射される線量は、悪性神経膠腫の場合には60Gyが一般的で、これを1日1回、1回につき2Gyに分けて照射します。ですから、週に5日の通常の分割照射であれば、治療期間は6週間になるということです。
低悪性度神経膠腫の場合は、照射量が45~55Gyと、悪性神経膠腫よりも少なくなります。1回あたりの線量は1・8~2Gyで、25~30回の分割照射を行います。
また、基本的に全脳照射は行わず、局所照射で治療します。照射範囲もマージンの幅が悪性神経膠腫よりも狭くてすみます。
悪性神経膠腫の場合、手術後に化学放射線療法が行われることがあります。抗がん剤治療としては、これまでニムスチンなどニトロソウレア系の薬が中心でしたが、昨今、テモゾロミドという薬が登場してきました。膠芽腫の術後療法として放射線治療とテモゾロミドを併用した化学放射線療法を行うことで、放射線治療単独よりも生存期間の延長が期待できると言われています。
こうした神経膠腫に対する放射線治療の急性期の副作用としては、照射部位の脱毛のほか、しばしば中耳炎が見られます。その他にも、頭痛や嘔吐、めまいなどの放射線宿酔が起こることもあります。いずれの症状も重症化することはほとんどありません。
髄膜腫での晩期副作用では放射線脳壊死や視力・視覚障害が起こる可能性がある
脳腫瘍の領域において、神経膠腫に次いで多いのが髄膜腫です。この病気は脳を包んでいる髄膜に発生する腫瘍で、脳そのものを圧迫するように大きくなります。その大部分は良性腫瘍ですが、なかには悪性のものもあります。ただし、良性でも徐々に大きくなっていくので、脳が圧迫されて死に至ることもあります。
ですから、良性・悪性を問わず、手術による切除が行われます。良性の場合は手術だけで治るケースがあります。しかし、脳の深い部分に発生しているときは、完全に摘出することができず、術後に通常の分割照射やガンマナイフ、定位放射線治療が行われることがあります。ただし、放射線治療によって視神経障害や下垂体機能の低下などが起こることもあるため、良性髄膜腫に対する術後照射は避ける傾向にあります。
悪性髄膜腫の場合は、手術による摘出と術後の放射線治療の組み合わせが基本です。また、手術の代わりとして、定位放射線治療が行われることがあります。
髄膜腫には、通常の分割照射では3門以上による3次元原体照射が行われています。その照射線量は全体で45~60Gy、1回あたり1・8~2Gyが一般的とされています。
髄膜腫は、低い線量でも効果が得られると言われていますが、悪性の場合は良性の場合よりも高い線量が不可欠だとされる報告もあります。ガンマナイフでは、腫瘍の外縁部への線量を11~18Gyに設定することが多いのですが、視神経などへの影響を抑えるため、十分な線量を照射できないことがあります。定位放射線治療では、1回1・8Gyを32回、または1回2Gyを26回などの分割照射が行われます。
こうした髄膜腫に対する放射線治療による副作用としては、急性期では中耳炎や放射線宿酔などが見られますが、重症化することは稀です。それに対し、晩期の副作用では、放射線脳壊死や視力・視覚障害などが起こる可能性があるものの、頻度は高くありません。
また、脳の上部にある腫瘍をガンマナイフで治療した場合には、治療終了後1~3カ月くらいに、稀に脳浮腫が起こることがあります。
下垂体腺腫に対する晩期副作用で最も問題になる下垂体機能の低下
脳腫瘍のなかの一種である下垂体腺腫は、その大部分が良性腫瘍です。しかし、稀に悪性のものがあります。また、良性でも周囲の組織を圧迫するように増殖し、さまざまな症状を引き起こします。
下垂体腺腫はホルモンの分泌が過剰になる機能性腺腫(プロラクチン産生腫瘍など)と、それ以外の非機能性腺腫に大別されます。
下垂体腺腫の治療法は、良性・悪性ともに手術による切除が基本です。手術ができない場合や、手術あるいは化学療法で治療しても再発を繰り返す場合、患者さんが手術を拒否している場合などには、腫瘍の縮小や機能性腺腫によるホルモン分泌過剰を正常化させるために放射線治療が単独で行われます。
また、術後の再発予防として、放射線が行われていますが、病院によっては、術後照射を行わないこともあります。
下垂体腺腫の治療は分割照射が一般的でした。しかし、正常組織への線量を減らせることから、最近では定位放射線治療やガンマナイフが用いられることが多くなっています。
通常、分割照射では腫瘍の周囲に最低でも5㎜のマージンをとって照射しますが、定位放射線治療ではその幅が2~4㎜、ガンマナイフでは1㎜になります。ただし、腫瘍と視神経の距離が5㎜以下しかない場合には、ガンマナイフによる治療は難しくなります。照射線量に関しては、通常、分割照射と定位放射線治療では、45~50Gyを25回に分けます。
ガンマナイフの場合、腫瘍のタイプによって線量が異なり、非機能性腺腫では腫瘍の周囲に当たる線量が15~20Gyですが、機能性腺腫では25Gy以上が望ましいとされています。
下垂体腺腫に対する放射線治療の急性期の副作用としては、照射部位への脱毛があります。晩期の副作用で最も問題になるのは、下垂体機能の低下で、成長ホルモンや副腎皮質刺激ホルモンなどの分泌が低下します。また、視覚障害や内頸動脈の狭窄、側頭葉の脳壊死などが稀に起こります。
聴神経腫瘍に対する照射は聴力低下などが起こる可能性がある
脳腫瘍のなかで、神経を包んでいる組織から発生する腫瘍を神経鞘腫と言います。神経鞘腫のなかでとくに多いのが聴神経腫瘍で、良性腫瘍であるものの、放置すれば周囲の組織を圧迫し、聴力を失ったり、頭痛や吐き気、歩行困難などの症状を引き起こしたりします。
その聴神経腫瘍の増大を抑制し、聴力を温存するために放射線治療が行われます。従来は手術による摘出が第1の選択肢でしたが、高い技術が求められ、聴力を失うことも多いという難点がありました。そのため、近年では放射線治療、とりわけ定位放射線治療やガンマナイフといったピンポイント照射が行われるケースが増えています。
一般的には、腫瘍の大きさが3㎝未満の場合には、ガンマナイフが、3~5㎝の場合には定位放射線治療が、5㎝を超える場合には分割照射が選択されます。ただし、聴力を温存できる確率は定位放射線治療のほうが高いため、3㎝未満の腫瘍に対しても定位放射線治療が選択される場合があります。
また、聴神経腫瘍に対する放射線治療は、CTやMRIで腫瘍の位置を確認したうえで、脳幹部や視神経などの重要な組織への線量が少なくなるように照射します。照射範囲はCTなどで確認した腫瘍を基本とし、ガンマナイフでは1㎜、定位放射線治療では2~4㎜のマージンを取ります。通常、分割照射では最低でも5㎜のマージンが必要になります。
聴神経腫瘍に対する放射線治療は、聴力温存の面で優れた治療と言えます。ただし、聴力の低下を完全に防げるわけでなく、どのような照射法でも、晩期の副作用として聴力低下が起こる可能性があります。その他にも、顔面神経や三叉神経の麻痺が見られることがあります。
さらに、稀に水頭症が起こることがあります。聴力低下を含め、何らかの副作用が起こる確率は10%以下とされています。
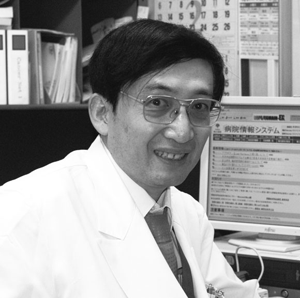
唐澤 克之(からさわ・かつゆき)
1959年東京生まれ。東京大学医学部卒業後。1986年スイス国立核物理研究所客員研究員。1989年東京大学医学部放射線医学教室助手。1993年社会保険中央総合病院放射線科医長。1994年東京都立駒込病院放射線科医長となり、2005年より現職。専門は放射線腫瘍学。特に呼吸器がん、消化器がん、泌尿器がん。日本放射線腫瘍学会理事、日本頭頸部腫瘍学会評議員、日本ハイパーサーミア学会評議員。近著に『がんの放射線治療がよくわかる本』(主婦と生活社)などがある。










