第26回 がんの放射線治療の副作用とその対策
~がん種別の最新の放射線治療と副作用 その⑮ 骨・軟部腫瘍、転移性骨腫瘍、転移性脳腫瘍~
放射線が持ち合わせる電離作用を駆使して悪性腫瘍を制御する放射線治療は、同時に正常細胞にもダメージを与え、さまざまな有害反応(副作用)を引き起こすことがあります。それでも、現在の放射線治療では、がん病巣への的確な照射が可能になり、放射線障害が確実に減少しています。したがって、放射線治療を始める前から、必要以上にその副作用を心配する必要はありません。
しかしながら、放射線治療についての正しい知識を持ち合わせ、治療後に発症する重い副作用を認識しておかなければ、大事な症状を見逃してしまいがちです。定期的な診察で早期発見に努めるとともに、いざというときの対処法を心得ておくことが、放射線治療を受けるうえでの得策だと言えます。
そのような趣旨で連載している26回目は、「がん種別の放射線治療と副作用」として、骨・軟部腫瘍、転移性骨腫瘍、転移性脳腫瘍を取り上げます。ぜひ、副作用対策にも役立てていただきたいと思います。
早期には皮膚炎や手術創の治癒の遅れ、治療後には骨粗鬆症に注意
今回、着目した3つのがん種のなかで、最初に骨・軟部腫瘍について述べます。
骨組織にできるがんを骨腫瘍、筋肉や脂肪組織などの軟部組織に生じたがんを軟部腫瘍または軟部組織肉腫といいます。この両者を合わせ、骨・軟部腫瘍と称します。骨肉腫やユーイング肉腫など、いろいろなタイプがあり、治療法はそのタイプによって異なります。
骨・軟部腫瘍の治療として、従来は、がんができた手や足を切断することが少なくありませんでした。最近は、がんとその周囲を広範囲に切除し、術前または術後の化学療法の併用により、可能な限り四肢を切断しないで治療するケースが増えています。
骨・軟部腫瘍に対する放射線治療は、手術や化学療法だけでは四肢の温存が困難な場合に、術前・術後、あるいは術中に、がんの縮小を目的として行われます。そのほか、がんが大き過ぎたり、年齢や合併症のために根治的な手術が難しかったり、完全に切除するのが難しい場所にがんができたりした場合にも、放射線治療が行われます。
照射時の姿勢は、安定性のよい仰臥位(上を向いて寝た状態)が基本です。下肢に照射する場合には、足台などを用いて足が動かないようにします。四肢への照射では、6MVのX線を用いますが、身体幹部や骨盤部には、よりエネルギーの高い10MVのX線を用います。
また、後腹膜腔など体の深部にがんがある場合には、さらに高エネルギーのX線が向いています。それと、皮膚のすぐ下にあるがんには、電子線が利用されることもあります。
照射する線量は、がんのタイプによって異なります。手術で明らかにがんを取り切れなかった場合、放射線感受性が比較的高いユーイング肉腫や横紋筋肉腫であれば、45~55Gyを25~30回に分けて照射するのが一般的です。
しかし、放射線感受性が低いタイプには、総線量を60Gyに上げて30回、患者さんの体力などが許せば、照射範囲を狭くして追加照射を行い、総線量を70Gyまで上げることもあります。なお、密封小線源治療(組織内照射)が外部照射との併用または単独で行われることもあります。
こうした骨・軟部腫瘍に対する放射線治療によって生じる主な副作用は、早い時期に起こるものとしては、皮膚炎や手術創の治癒の遅れが見られます。また、骨に40Gy以上照射したときに、治療後半年以上が過ぎてから骨粗鬆症が起こることがあります。
照射部位に応じて、咽頭炎・食道炎・腸炎などが起こることがある
転移性骨腫瘍は、他の部位にできたがんが骨に転移したものです。さまざまながんが骨転移を起こしますが、比較的多いのが肺がん・乳がん・前立腺がんです。
骨に転移したがんが大きくなると、病的な骨折や脊髄への圧迫、脳神経症状が起こります。それらの症状を予防、あるいは改善してQOL(生活の質)を維持するのが放射線治療の目的です。その際、原発巣の部位や病期、患者さんの全身状態などを問いませんが、根治を目的とした治療ではありません。ただ、症状の原因であるがんを縮小させることができる点で、モルヒネなどの鎮痛剤より優れています。
治療の実際としては、転移巣に対して、8Gyで1回、あるいは4Gyを6回か3Gyを10回照射するのが一般的です。ただし、頸椎への照射は左右対向二門、胸部や腰部の脊椎への照射は後方一門または前後対向二門で行います。
そして、長期の余命が期待できる場合には、総線量を上げてがんの縮小を目指します。その場合には、2・5Gyで15回、または2Gyで25回の照射が多いようです。
転移性骨腫瘍は、痺れや感覚麻痺、下肢の脱力感といった脊髄圧迫症状に対しては、可能な限りすみやか(48時間以内が目安)に放射線治療を行う必要があります。というのも、麻痺が常態化してしまうと、改善率が低下してしまうからです。
また、転移性骨腫瘍の症状のなかで最もよく見られるがん性疼痛に対しての放射線治療は、80%以上の寛解率があるとされています。
転移性骨腫瘍に対する放射線治療の主な副作用は、照射部位に応じて、咽頭炎や食道炎、腸炎などが起こることがあります。ただし、線量が少ないため、重い副作用が起こることはごく稀です。
頭痛・吐き気・嘔吐や頭蓋内圧亢進症状にも留意が必要
最新のピンポイント照射が最も得意とするがんの一つが転移性脳腫瘍です。この転移は、肺がんと乳がんが引き起こしやすいのが知られています。また、脳には血液脳関門という独特の仕組みがあり、そこには抗がん剤などの薬剤が届きにくいため、放射線治療が大きな役割を果たしています。
転移性脳腫瘍の場合、転移巣が一つで、かつ原発巣の状態が落ち着いていれば、比較的長い予後が期待できます。そのケースでは、手術が有効です。しかし、開頭手術を行うためには患者さんに十分な体力が求められますし、後遺症の問題もあります。
放射線治療は、手術の対象とならない人に対し、麻痺や頭痛、吐き気などの症状を改善し、QOLのレベルを維持・向上させることを目的として行われます。また、ガンマナイフ(誤差1㎜という高精度で、がん細胞に放射線を照射する装置)やリニアック(X線照射装置)による定位放射線治療などのピンポイント照射であれば、手術と同等の治療効果が期待でき、がんを完全に破壊できることもあります。
転移性脳腫瘍に対する放射線治療には、主に二つの方法があります。一つは脳全体に放射線を当てる「全脳照射」です。この場合、がんが3㎝以上、あるいはいくつもの転移巣がある人に選択されます。もう一つはガンマナイフなどの「ピンポイント照射」です。この場合、がんが3㎝以下、あるいは転移巣の数がおよそ5個以内の人が対象となります。
前者の全脳照射は、転移性脳腫瘍で最も一般的な治療法です。通常、30Gyを10回、または37・5Gyを15回に分けて照射します。ただし、全身状態が良好な場合には、総線量を40~50Gyに増やすこともあります。反対に、全身状態が悪い場合には、20Gy程度に落とします。その照射法は、左右対向二門照射です。また、全脳照射では、ステロイド剤や浸透圧利尿剤などが併用されることもあります。
後者のピンポイント照射は、ガンマナイフのように、一度に大量の放射線をまとめて照射する方法と、何回かに分割して照射する方法があります。一括照射する場合は、16~25Gyを1回、照射するだけで治療が終わります。ただし、頭部にコリメータヘルメットを固定しなければなりません。分割照射する場合は、総線量や線量分割が医療機関によって異なります。一般に、30~35Gyを3回に分けるなど、総線量は一括照射に比べて多くなります。
また、近年は、陽子線治療も行われています。
転移性脳腫瘍に対する放射線治療の主な副作用は、初期に頭痛や吐き気、嘔吐などのほか、脳浮腫による頭蓋内圧亢進症状が起こることがあります。ただし、頭蓋内圧亢進症状は放射線治療によって起こるというよりも、転移性脳腫瘍の人は多少の脳腫瘍により脳圧亢進を起こしていることが多いようです。そこに放射線治療を行うことで、それが進行して起こるケースが少なくないようです。その予防には、治療前にステロイド剤や浸透圧利尿剤を服用します。
先述の全脳照射の副作用の一つに、認知能力の低下があります。これは、1回あたりの線量と治療後の経過時間によって影響されると言われており、必要であれば1回あたりの線量は2・5Gy以下に抑えるようにしています。それに対し、定位照射(ピンポイント照射)は副作用が少ない治療法です。最近、がん患者さんの予後改善によって、よりピンポイント照射が多く用いられるようになってきています。ただし、まったく副作用のリスクがないわけではなく、稀に脳浮腫を引き起こすこともあります。
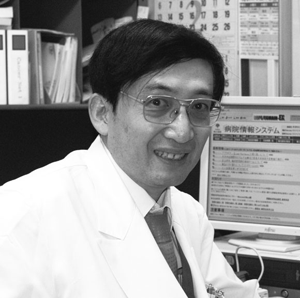
唐澤 克之(からさわ・かつゆき)
1959年東京生まれ。東京大学医学部卒業後。1986年スイス国立核物理研究所客員研究員。1989年東京大学医学部放射線医学教室助手。1993年社会保険中央総合病院放射線科医長。1994年東京都立駒込病院放射線科医長となり、2005年より現職。専門は放射線腫瘍学。特に呼吸器がん、消化器がん、泌尿器がん。日本放射線腫瘍学会理事、日本頭頸部腫瘍学会評議員、日本ハイパーサーミア学会評議員。近著に『がんの放射線治療がよくわかる本』(主婦と生活社)などがある。










