第13回 がんの放射線治療の副作用とその対策
~がん種別の最新の放射線治療と副作用 その② 頭頸部がん~
放射線が持ち合わせる電離作用を駆使して悪性腫瘍を制御する放射線治療は、同時に正常細胞にもダメージを与え、さまざまな有害反応(副作用)を引き起こすことがあります。それでも、現在の放射線治療では、がん病巣への的確な照射が可能になり、放射線障害が確実に減少しています。したがって、放射線治療を始める前から、必要以上にその副作用を心配する必要はありません。
しかしながら、放射線治療についての正しい知識を持ち合わせ、治療後に発症する重い副作用を認識しておかなければ、大事な症状を見逃してしまいがちです。定期的な診察で早期発見に努めるとともに、いざというときの対処法を心得ておくことが、放射線治療を受けるうえでの得策だと言えます。
そのような趣旨で連載している13回目は、「がん種別の放射線治療と副作用」として頭頸部がんを取り上げます。ぜひ、副作用対策にも役立てていただきたいと思います。
4つに大別できる頭頸部がんのおのおのの特徴
頭頸部がんは、口腔や喉など耳鼻咽喉領域にできるがんの総称です。このがん種はがん全体の約5%と、それほど多くありません。しかし、次のような共通点があり、根治とQOL(生活の質)の両立が難しいのが特徴です。
- ①聴覚・平衡覚・味覚などの重要な感覚器を含む。
- ②呼吸・発声・摂食・嚥下(えんげ)など、生命の維持や社会生活を営むうえで欠かせない機能に密接に関係している。
- ③組織に余裕がなく、切除した場合に機能障害が残りやすい。
- ④衣服でおおわれず、露出している部分が多い。
頭頸部がんは発生部位によって、がんの性質が異なるので治療法も違ってきますが、比較的、放射線が効きやすい扁平上皮がんが多く、QOLの面で有利な放射線治療が重要な役割を果たしています。
その頭頸部がんは、主に舌がん・咽頭がん・喉頭がん・口腔底がんの4つに大別できます。
舌がんは、口腔にできるがんのなかで、最も頻度が高いがん種です。通常、舌がんと呼ばれるのは舌の前方3分の2にできるものを言い、後方の舌根部にできるのは中咽頭がんに含まれます。
続いて咽頭がんですが、咽頭は上部・中部・下部の3ブロックに分けられ、それぞれの機能やがんの発生原因が異なるため、治療法も異なってきます。ただ、大部分の咽頭がんは比較的、放射線が効きやすい扁平上皮がんであることや、手術では機能温存が難しいことなどから、放射線治療の役割が大きくなっています。
喉頭がんは、頭頸部がんのなかでは発生頻度が高いがんです。喉頭は、声門部を中心に声門上部と声門下部の3つの領域に分けられます。そのなかで、最もがんができやすいのは声門部で、喉頭がんの約70%を占めています。残りの大部分は声門上部がんで、声門下部がんは稀です。
口腔底がんは、舌の裏側のU字部分にできるがんです。初期症状に乏しいため、発見された時点で40%程度にリンパ節転移が見られます。治療法は手術による切除が中心ですが、機能や形態の温存性に優れている放射線治療が行われるケースも増えています。
最大径4㎝以下は根治的照射の対象になる舌がん
舌がんは、リンパ節転移がなく、がんの最大径が4㎝以下であれば、放射線治療単独(密封小線源治療)による根治的照射の対象になります。がんが3㎝以下ならば手術でも部分的に切除することで根治が可能で、嚥下障害や構音障害は残りません。ただし、3㎝以上になると、機能障害が起こりやすくなります。
がんが4㎝を超える場合には、手術が優先され、術後療法として放射線照射が併用されます。何らかの理由で手術ができない場合には、下顎骨などの周辺組織に浸潤していなければ密封小線源治療が、浸潤があれば外部照射が行われます。また、術前照射でがんを小さくしてから手術が行われるケースもあります。
また、頸部リンパ節などに転移がある場合、基本的に原発巣とリンパ節を切除しますが、原発巣を放射線治療で治し、リンパ節だけを切除することもあります。その他、がんが進行して根治が期待できないケースでは、症状の緩和を目的として放射線治療が行われます。
舌がんに対する密封小線源治療は、舌に針状の線源を刺す組織内照射が用いられます。線源としては、イリジウム192が使われることが多いようです。
イリジウム192には、低線量率の線源と高線量率の線源があります。前者の場合は50~70Gyを4~8日に分けて照射し、後者の場合は60Gyを1日2回、5日間で照射するのが原則です。舌の表面近くにできた小さながんであれば、粒状の金198線源を永久刺入する方法もあります。この場合の総線量は85~90Gyが標準的です。なお、照射時には下顎骨を放射線から守るため、スペーサーと呼ばれる器具を口腔内に装着します。それと、線源を刺入するために、局所麻酔、あるいは全身麻酔が必要になります。
外部照射は、左右対向2門照射が基本です。総線量は66~70Gyで、1回あたり1・8~2Gyを照射します。また、多くの場合、40~50Gy前後でがんが縮小するので、それに合わせて照射範囲を縮小します。そして、がんが縮小した時点で組織内照射に切り替えることもあります。
急性期の副作用としては、口腔・咽頭の粘膜炎、唾液の分泌障害、味覚障害などが見られます。ただ、外部照射に比べ、組織内照射では放射線が当たる範囲が狭いため、粘膜炎は線源を刺入した周辺にのみ起こります。
晩期の副作用では、粘膜の難治性潰瘍や下顎骨の骨髄炎・壊死への注意が必要です。これらの障害についても、組織内照射のほうが外部照射に比べて発生頻度が明らかに少なくなります。
化学放射線療法が基本となる咽頭がん
上部・中部・下部の3ブロックに分けられる咽頭がんのうち、上咽頭がんは、元々、手術が困難な部位に発生すること、発見されたときには進行していることが少なくありません。したがって、進行度を問わず放射線治療が第1選択肢となり、根治的照射が行われます。ただし、放射線だけでは根治の可能性が十分ではなく、抗がん剤治療もよく効くとされているので化学放射線療法が基本になっています。また、遠隔転移があるときには、原則として放射線治療の対象になりませんが、上咽頭がんでは化学療法との併用で局所制御が期待できる場合もあります。
上咽頭がんは、周囲への浸潤や遠隔転移を起こしやすいので、頭蓋底や周辺リンパ節などを含めて照射する全頸部照射がよく用いられます。その場合には、1回1・8~2Gyの通常分割照射で40~50Gy程度までは頸部全体に照射し、それ以降はがんの原発部位と周囲のリンパ節に的を絞って60~70Gyまで照射します。
その他、最初からがんやリンパ節だけに照射することもあります。その場合も、線量が40~50Gyに達した時点で、がんの縮小に合わせて照射範囲を修正します。さらに、周囲への浸潤がなく、がんが小さい場合には組織内照射や腔内照射、定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)が行われることもあり、良好な成績が報告されています。
中咽頭がんでは、早期がんは放射線治療単独での根治が期待できます。しかし、進行がんでは手術が必要で、術前または術後に放射線治療が併用されます。ただし、早期がんでも、手術による機能障害が軽度ですむケースでは、手術が選択されることもあります。
中咽頭がんの場合、4~6MVの比較的弱いX線や電子線が使われます。最初は脊髄を含めた広い範囲に40~45Gyまで照射し、その後、脊髄を除外した範囲に65~70Gyまで照射します。基本的には通常分割照射が行われるケースが増え、治療成績が向上しています。なお、外部照射の他に、密封小線源治療が行われることもあります。
下咽頭がんでも、早期がんに対して放射線治療単独で根治的照射を行い、進行がんには手術の前後に放射線治療が行われます。その際には、化学療法が用いられることもあります。
下咽頭がんもリンパ節転移を起こしやすいのが特徴です。したがって、根治的治療と術前照射では、頸部のリンパ節をすべて含めた広い範囲に40~46Gyを照射します。根治的治療の場合、その後に照射範囲から脊髄をはずして66~70Gyまで照射が行われます。術後照射の場合、照射範囲は術前照射と同じですが、全体の線量は術前照射よりやや多くなります。
咽頭がんの副作用は、照射範囲が広くなることが多いため、その分、起こりやすくなります。急性期の副作用としては、大部分の人に口腔や喉の炎症による乾燥感・痛みなどが起こります。また、放射線皮膚炎が見られることもあります。晩期の副作用では、唾液の分泌低下が起こります。また、稀に慢性中耳炎・網膜症などが見られることもあります。
早期がんが根治的照射の対象となる喉頭がん
喉頭がんの放射線治療は、日本ではリンパ節転移のない早期がんが、根治的照射の対象となります。喉頭がんのなかで最も多い声門がんは早期発見率が高く、リンパ節転移を起こしにくいので、早期がんであれば放射線治療で根治が可能です。
それに対し、進行がんには、手術で咽頭を摘出した後で術後照射を行うのが基本です。ただし、この場合、発声機能を温存することはできません。放射線治療単独で進行がんを治すことは困難ですが、化学療法との併用で効果がアップすることが報告されており、進行がんでも手術せずに化学放射線療法が選択されるケースも増えています。
喉頭がんに対する放射線治療は、通常、左右対向2門照射で行われます。使用される放射線は通常4~6MVの比較的エネルギーの弱いX線が用いられます。
照射スケジュールは、1回1・8~2Gyの通常分割照射が多く、進行がんに対しては過分割照射が行われることがあります。その照射線量は、通常分割照射による根治的照射でステージⅠのがんであれば60~66Gy、ステージⅡのがんであれば66~70Gyが標準治療です。その際、過分割照射の場合には、線量がやや多くなります。過分割照射は治療効果が向上する反面、急性期の副作用の頻度が高くなります。
進行性の喉頭がんに対する化学放射線療法では、放射線治療の前か後、あるいは同時に化学療法を行う3つの方法があります。このうち、手術を回避できる確率は同時併用法がやや高くなりますが、生存率はあまり変わりません。また、化学放射線療法は、併用時期を問わず、放射線治療単独に比べ、重い副作用が起こりやすくなります。
喉頭がんに対する放射線治療の主な副作用としては、急性期では粘膜の炎症による声がれや嚥下困難が知られています。ただし、そのほとんどが一時的なもので、時間が経てば症状は消えてしまいます。
早期であれば放射線治療単独での根治が期待できる口腔底がん
口腔底がんにおいては、多くの場合、リンパ節転移のない早期がんであれば、放射線治療単独での根治が期待できます。ただし、がんが小さく、リンパ節転移がなくても、歯肉や下顎骨に向かって浸潤している場合は根治的照射の対象にはなりません。その場合には手術が行われ、再発予防のために術後照射が行われます。
口腔底がんに対する放射線治療は、外部照射または密封小線源治療が用いられます。密封小線源治療としては、組織内照射のほか、病巣部に線源を密着させるモールド照射という方法もあります。一般にがんの厚さが数㎜以内のときはモールド照射が、それ以外の場合には組織内照射が選択されます。
その治療成績ですが、リンパ節転移のない早期がんでは、ステージⅠであれば90%、ステージⅡ~Ⅲであれば70~80%の高い局所制御率が報告されていて、生存率も良好です。ただし、リンパ節転移があるときには、生存率が50%程度に低下します。
こうした治療の主な副作用としては、急性期では口腔や咽頭の粘膜炎、急性期・晩期を通じては唾液分泌障害、味覚障害などが見られます。
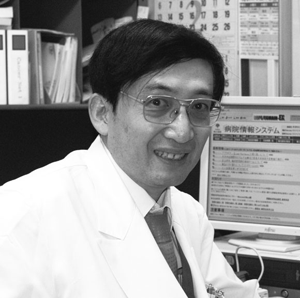
唐澤 克之(からさわ・かつゆき)
1959年東京生まれ。東京大学医学部卒業後。1986年スイス国立核物理研究所客員研究員。1989年東京大学医学部放射線医学教室助手。1993年社会保険中央総合病院放射線科医長。1994年東京都立駒込病院放射線科医長となり、2005年より現職。専門は放射線腫瘍学。特に呼吸器がん、消化器がん、泌尿器がん。日本放射線腫瘍学会理事、日本頭頸部腫瘍学会評議員、日本ハイパーサーミア学会評議員。近著に『がんの放射線治療がよくわかる本』(主婦と生活社)などがある。










