第21回 がんの放射線治療の副作用とその対策
~がん種別の最新の放射線治療と副作用 その⑩ 子宮がん~
放射線が持ち合わせる電離作用を駆使して悪性腫瘍を制御する放射線治療は、同時に正常細胞にもダメージを与え、さまざまな有害反応(副作用)を引き起こすことがあります。それでも、現在の放射線治療では、がん病巣への的確な照射が可能になり、放射線障害が確実に減少しています。したがって、放射線治療を始める前から、必要以上にその副作用を心配する必要はありません。
しかしながら、放射線治療についての正しい知識を持ち合わせ、治療後に発症する重い副作用を認識しておかなければ、大事な症状を見逃してしまいがちです。定期的な診察で早期発見に努めるとともに、いざというときの対処法を心得ておくことが、放射線治療を受けるうえでの得策だと言えます。
そのような趣旨で連載している21回目は、「がん種別の放射線治療と副作用」として、子宮がんを取り上げます。ぜひ、副作用対策にも役立てていただきたいと思います
子宮頸がんへの放射線治療は手術と同等の効果がある
今回、着目する子宮がんには、子宮の入り口にできる子宮頸がんと、子宮の奥にできる子宮体がんがあります。それぞれ性質が異なるため、治療法も違います。
子宮頸がんは、病期を問わず放射線治療と手術のどちらも行われます。それに対し、子宮体がんは、手術不可能な場合や術後に放射線治療が行われます。ですので、本稿では、子宮頸がんと子宮体がんに分けて、説明いたします。
子宮頸がんの治療には、手術、放射線治療、化学療法があります。そのなかで、放射線治療が有効なのは、がんの性質や状態などにより手術ができない場合です。ただし、手術が可能でも放射線治療が有効なケースがあります。また、放射線治療を化学療法と組み合わせると高い効果が得られる場合もあります。
子宮頸がんへの放射線治療の効果は高く、手術と同じ治療効果があります。Ⅰ~ⅣA期までのすべての病期が放射線治療単独の根治的照射の対象となりますが、日本ではⅠ~Ⅱ期は手術、Ⅲ~Ⅳ期は放射線治療を行うのが一般的です。
根治的照射のほかに、手術後に、細胞レベルで残存している可能性のあるがんを根絶する目的で、予防的照射が行われることもあります。術後照射の場合には腔内照射を併用しない場合が多く、骨盤照射によって、小腸などの腸管へ照射される体積が無視できないため、強度変調放射線治療といって、高い線量が照射される範囲から腸管が含まれる部分を大きく減らし、腸管の有害事象を減らす放射線治療を行っている施設もあります。写真1・2に従来の放射線治療による線量分布と強度変調放射線治療による線量分布の比較を示します。

写真1 子宮頸がんー従来の放射線治療

写真2 子宮頸がんー強度変調放射線治療
晩期の副作用には腸管の狭窄や癒着、腸閉塞、潰瘍などがある
子宮頸がんに対する根治目的とした放射線治療では、外部照射と腔内照射の併用が基本です。その実際の照射は、骨盤内リンパ節と子宮傍組織に浸潤したがんを対象として、骨盤部に外部照射を行います。外部照射は、直交四門照射が基本ですが、前後対向二門照射が行われることもあります。
全骨盤照射は、1日約2Gyで週5回行い、総線量20~40Gyで中央遮蔽に切り替えます。中央遮蔽で1日約2Gy、週5回、総線量約50Gyにします。
術後照射の場合、1日1回1・8Gyで25回(総線量50・4Gy)、または1回2Gyで25回照射(総線量50Gy)するのが標準的です。
腔内照射を併用する場合には、骨盤部への外部照射の途中から腔内照射に切り替えます。腔内照射は、必要に応じて高線量率照射と低線量率照射が使い分けられます。その際、照射する総線量は、低線量率照射のほうが多くなります。
腔内照射を行うときは、腟内にガーゼをたくさん入れて直腸への線量を下げるための注力がなされます。
外部照射と腔内照射を合わせた総線量は病期によって異なりますが、早期のがんほど腔内照射の比率が高くなります。そして、腔内照射の占める割合によっては、腔中央に幅3~4㎝の遮蔽板を入れ、直腸や膀胱への影響を防ぐことがあります。
また、がんの状態によっては、骨盤部への外部照射が終わった後、腹部リンパ節にも外部照射を行うことがあります。
なお、治療開始に先立ち、正確に治療を再現できるように位置決め作業(シミュレーション)を行い、その1~2日後から治療を開始します。
進行しているがんの場合は、シスプラチンを中心とした抗がん剤との併用が一般的です。
子宮頸がんの5年生存率は、Ⅰ期では80~90%、Ⅱ期では60~80%、Ⅲ期では40~60%、ⅣA期では10~40%です。
主な副作用としては、治療の早い段階で見られるものに腸炎(下痢・血便)や照射部位の皮膚炎、放射線宿酔、頻尿、排尿時痛などが挙げられます。抗がん剤を併用して治療する場合などには、骨髄の障害により、白血球・血小板の減少、貧血などが起きることがあります。
これらの多くは軽症で、内服薬や外用薬を用いて経過を観察します。そして、治療終了後には軽快することがほとんどです。
晩期の副作用には、腸管の狭窄や癒着、腸閉塞、潰瘍などがあります。
子宮体がんの根治的放射線治療は年齢、合併症などにより手術が不能もしくは困難な場合に行われる
子宮体がんの治療は手術による切除が中心となります。というのは、子宮体がんの約85%が切除可能な早期の状態で見つかっていることがその理由の一つです。しかし、子宮体がんは、腺がんのなかでは放射線感受性が良好ながん種です。
子宮体がんに対する放射線治療は、肥満や糖尿病、脳血管疾患などの合併症によって手術ができないか困難な場合に、病期に拘らず行われることがあります。その際は外照射と腔内照射の併用もしくは各々の単独治療として行われます。
術後照射は、手術後の再発を防ぐために、術後照射を行うことがあります。とくに、病期や浸潤範囲、子宮の大きさなどから見て、再発の危険性が高いと思われる場合によく行われます。
子宮体がんに対する放射線治療の実際として、腔内照射は、早期の根治治療のほか、がんの部位によっては、術後照射でも外部照射と併用されることがあります。
腔内照射では、子宮腔内に複数の線源を挿入します。その際、事前に子宮内腔のがん組織を可能な限り掻き出し、子宮筋層の厚みを一様にして空間を確保するようにします。
一般に、線源は2~4本挿入されますが、子宮の大きさによっては、それよりも少なくなることがあります。最近では、アプリケータなど、腔内照射の技術開発が進み、より高い治療効果が期待されています。
腔内照射を併用する場合、外部照射は進行して子宮の外に広がった場合の根治的照射や、術後に行われます。根治的照射の場合、まず全骨盤照射を行った後、幅3~4㎝の中央遮蔽を使った照射に切り替えます。
全骨盤照射は、1日約2Gyで週5回行い、総線量20~40Gyで中央遮蔽に切り替えます。中央遮蔽で1日約2Gy、週5回、総線量約50Gyにします。
術後照射の場合、1日1回1・8Gyで25~28回 (総線量45~50・4Gy)、または1回2Gyで25回照射(総線量50Gy)するのが標準的です。また術後照射に強度変調放射線治療を用いる場合もあります。
晩期の副作用には、大腸・直腸の狭窄や癒着、潰瘍、皮膚の荒れ、むくみ、頻尿、血尿などがある
治療成績で言えば、根治的照射の症例は多くありませんが、Ⅰ期で75~100%、Ⅱ期で30~100%と早期の場合は良好です。一方、術後照射では、Ⅰ期で65~80%、Ⅱ期で50~70%、Ⅲ期でも50%に達しています。
ちなみに、子宮体がんの病期は、次のようになっています。
- Ⅰ期:がんが子宮体部に限局していて、子宮頸部やその他の部位に認められない。
- Ⅱ期:がんが子宮体部を越えて子宮頸部に広がっているが、子宮の外に出ていない。
- Ⅲ期:がんが子宮外に広がっているが、骨盤外には広がっていない。または、骨盤内あるいは大動脈周囲のリンパ節に転移がある。
- Ⅳ期:がんが骨盤を越えて他の部位へ広がるか、または膀胱、あるいは腸の内腔を侵すもの。
子宮体がんへの放射線治療の主な副作用としては、急性期には、腸炎や放射線宿酔、皮膚炎、泌尿器系障害、白血球・血小板減少などの骨髄抑制などが現れます。急性期の副作用の多くは軽症で、その大部分が治療終了後に軽快します。
晩期には、大腸・直腸の狭窄や癒着、潰瘍、皮膚の荒れ、むくみ、頻尿、血尿などが起きることがあります。
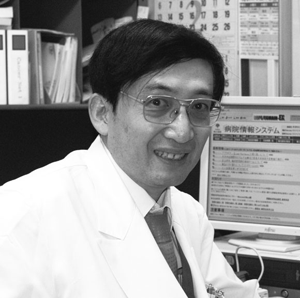
唐澤 克之(からさわ・かつゆき)
1959年東京生まれ。東京大学医学部卒業後。1986年スイス国立核物理研究所客員研究員。1989年東京大学医学部放射線医学教室助手。1993年社会保険中央総合病院放射線科医長。1994年東京都立駒込病院放射線科医長となり、2005年より現職。専門は放射線腫瘍学。特に呼吸器がん、消化器がん、泌尿器がん。日本放射線腫瘍学会理事、日本頭頸部腫瘍学会評議員、日本ハイパーサーミア学会評議員。近著に『がんの放射線治療がよくわかる本』(主婦と生活社)などがある。








