第14回 がんの放射線治療の副作用とその対策
~がん種別の最新の放射線治療と副作用 その③ 甲状腺がん・食道がん~
放射線が持ち合わせる電離作用を駆使して悪性腫瘍を制御する放射線治療は、同時に正常細胞にもダメージを与え、さまざまな有害反応(副作用)を引き起こすことがあります。それでも、現在の放射線治療では、がん病巣への的確な照射が可能になり、放射線障害が確実に減少しています。したがって、放射線治療を始める前から、必要以上にその副作用を心配することはありません。
しかしながら、放射線治療についての正しい知識を持ち合わせ、治療後に発症する重い副作用を認識しておかなければ、大事な症状を見逃してしまいがちです。定期的な診察で早期発見に努めるとともに、いざというときの対処法を心得ておくことが、放射線治療を受けるうえでの得策だと言えます。
そのような趣旨で連載している14回目は、「がん種別の放射線治療と副作用」として、甲状腺がんと食道がんを取り上げます。ぜひ、副作用対策にも役立てていただきたいと思います。
甲状腺未分化がん・分化がんに対する放射線治療
甲状腺がんは、乳頭がん・濾胞がん・髄様がんといった分化がん、未分化がんなどに分けられます。分化がんが一般に治りやすいのに対し、未分化がんは悪性度が高く、治癒が見込めないケースがほとんどです。
これらのうち最も多いのが乳頭がんで、全体の70~80%を占めています。そのなかの約90%は増殖が遅くて治癒率の高い低危険度群で、遠隔移転を起こす高危険度群は10%程度にすぎません。
なお、乳頭がんはリンパ節転移を起こしやすいがんです。ただ、リンパ節転移の有無が、必ずしも治癒率の低下に結び付くとは限らないのが特徴の1つです。
分化がんの治癒では手術で切除するのが基本で、放射線治療は再発予防を目的とする術後照射が行われます。しかし、高危険度群に対しては、甲状腺をすべて摘出して術後照射を行うのが一般的です。また、低危険度群では可能な限り切除範囲を小さくし、術後照射を行わないことが多いようです。
ちなみに、アメリカなどでは、低危険度群に対しても、高危険度群と同じ治療を行うのが基本となっています。日本式とアメリカ式のどちらが良策なのか、という比較研究は行われていないので、それは明確でありません。
近年は、EBM(科学的根拠に基づく医療)という考え方が医療の基本になっていますが、分化がんの場合、日本式とアメリカ式の双方の治療法でも良好な成績が得られているので、両者の比較が行われていないのです。
未分化がんの治療も手術が基本ですが、実際には発見時に遠隔転移などを起こしているケースがほとんどで、そのような場合には化学療法や放射線治療が選択されます。
甲状腺がんに対する放射線治療の中心であるアイソトープ内服療法
甲状腺がんの放射線治療では、アイソトープ内服療法が中心になります。この治療法は、放射性同位元素(アイソトープ)をカプセルに包み、一般の薬剤と同じように服用するものです。主に手術で取り切れなかった残存腫瘍による再発予防や、手術後の再発、あるいは肺や骨などへの遠隔転移の治療にも用いられます。
甲状腺は消化管から吸収されたヨウ素(ヨード)から甲状腺ホルモンを合成します。この「ヨードを取り込む」という性質は、甲状腺の正常組織だけでなく、甲状腺にできるがんにも受け継がれる場合があります。そこで、「ヨウ素131」という放射性同位元素を内服して甲状腺に取り込ませます。その際、放出される放射線によって、がん細胞を叩こうというのが、この治療法の狙いです。
この方法では、がん細胞のほうから放射線源を取り込んでくれるので、がんがどこにあっても、またいくつあっても問題になりません。さらに、放出される放射線は数ミリ程度の範囲にしか作用しないので、周囲の正常組織への影響が少なく、副作用のリスクを最小限に抑えられます。加えて、繰り返して治療を行うことができるのも、この治療法の大きな特徴です。
先述のように、甲状腺はヨウ素を取り込む性質があるため、ヨウ素の放射性同位元素であるヨウ素131を内服すると、甲状腺にヨウ素131が蓄積され、がんに対して集中的に放射線を浴びせます。この治療法は簡便で苦痛のない優れた治療法です。ただし、甲状腺の正常組織が残っているとヨウ素131がそこに取り込まれてしまうため、アイソトープ内服療法を行う場合には、事前に手術で甲状腺を摘出することが必要です。
甲状腺がんの治療は手術による摘出が基本ですが、悪性度の低いがんに対しては甲状腺をすべて摘出せず、一部を残す場合もあります。そのようなケースにおいて、がんが再発し、ヨウ素131による治療を行うようになった場合には、再度、手術を受け、残った甲状腺を摘出してから内服療法を行います。
アイソトープ内服療法の線量と副作用
転移したがんは、最初に発生した部位の組織と同じ性質を持ちます。したがって、甲状腺がんが肺などに転移していても、血液中のヨウ素131が取り込まれて原発巣と同時に治療することができます。
また、治療の4週間ほど前から食事によるヨウ素を含む食べ物、および甲状腺ホルモン剤を摂取しないようにして、甲状腺がヨウ素を取り込みやすい状態にしておきます。それと、治療前に1度、ヨウ素131を取り込むか否かを調べ、服用量を決定します。
なお、治療後も一定期間、ヨウ素を含む食品の摂取を控える必要があります。こうしたことをしたうえで、内服予定日に専用の病棟に入院し、ヨウ素131を内服するのです。
アイソトープ内服療法の線量は、術後の再発予防を目的とする場合には1110~3700MBq(メガベクレル)、転移がんに対する治療の場合には3700~5550MBqが標準的です。
リンパ節転移への治療で、転移巣がヨウ素を取り込まない場合には、外部照射が行われることもあります。その際、がんを切除した部分に頸部リンパ節と胸部の上縦隔リンパ節を加えた範囲に、50~60Gyを1回あたり2Gyで照射します。
未分化がんは要素を取り込まないので、放射線治療は外部照射しか選択肢がありません。標準的な照射方法はなく、60Gyを30回に分ける通常分割照射が行われます。
アイソトープ内服療法では、唾液腺に分泌障害や放射線宿酔、骨髄抑制などの副作用が早期に現れることがあります。いずれも一過性のもので、時間の経過とともに治っていきます。そのほか、肺線維症が起こることもあり、注意が必要です。
外部照射では、急性の副作用としては、皮膚炎や局所的な粘膜炎、嚥下困難などがあります。晩期の副作用としては食道や気道の機能障害が起こることがあります。
ヨウ素131を内服すると、少量の放射線が体外に発散されます。そのため、周囲の人に放射線が当たらないように、医師の許可があるまで室外に出ることや面会ができません。そして、毎日、放出される放射線の量を測定し、基準値以下になったら退院できるようになります。内服する量にもよりますが、入院期間は概ね3~5日程度とされています。
食道がんに対する放射線治療
食道がんの治療は、従来から手術が基本とされています。したがって、放射線治療は手術ができないほど進行した患者さんが対象でした。しかし、放射線感受性が比較的高いこと、化学療法との併用で手術と同程度の治療成績が得られることなどにより、近年は手術が可能なケースでも化学放射線療法が選択されるケースが増えています。
食道がんに対する放射線治療は、根治的照射と緩和的照射があります。根治照射は、主に早期がんが対象になりますが、がんが気管や大動脈にまで浸潤して手術ができないケース、手術が可能でも手術を臨まないケースなど、すべての病期で根治的照射が行われます。なかには、手術が不可能なほど進行している患者さんでも化学放射線療法で完治するケースがあります。
緩和的照射は、がんのために食道の内腔が狭くなり食事が摂れない場合など、遠隔地転移があって根治不能な人に行われます。それに対し、緩和的照射では、外部照射と腔内照射が単独、あるいは併用で行われます。その際、がんが浅い部分(粘膜層)に留まっている場合には、腔内照射だけで根治可能なケースもあります。しかし、それよりも深い部分にまで達している場合には、リンパ節転移を予防するため、腔内照射の前に外部照射を行います。早期がんには外部照射だけで根治を目指す場合もあります。
なお、早期がんに対しては、内視鏡的切除術(EMR)が第1選択肢となります。ただし、EMRを行うには、がんの最大径が2㎝以下、広がりが食道前周の3分の1以下であることが必要です。それ以上の大きな場合は、放射線治療の対象となります。
食道がんの放射線治療の副作用
食道がんにおいて、早期のものに対する腔内照射では、線源として主に高線量率のイリジウム192が用いられ、28~35Gyを照射します。進行性のものの場合は、高線量率のほかに低線量率の腔内照射が行われることもあります。いずれの場合も、外部照射に引き続いて行われます。なお、腔内照射の1回あたりの線量は、高線量率では4Gy、低線量率では6Gyが標準になります。
外部照射では、化学放射線療法の場合は、60Gyを30回に分けて照射するのが一般的です。放射線治療単独の場合には、70Gyまで線量を増やすこともあります。その際の照射法は6~10MVのX線による対向二門照射が中心で、40~45Gyまでは脊髄を含め、その後、脊髄を避けて照射します。
近年は、心臓などへの線量を減らすために、多門照射が行われることもあります。
手術で取り切れなかったがんに対する術後照射、あるいは手術後の再発に対しても、60Gy程度の外部照射が行われます。ただし、術後の化学放射線治療では、50Gyほどに線量を減らすこともあります。
化学療法を併用するタイミングとしては、放射線と化学療法を同時に行う方法の効果が高く、外部照射を行いながら、フルオロウラシルやシスプラチンなどの抗がん剤を使用します。
緩和的照射でも化学放射線療法が基本ですが、体力が低下していて抗がん剤の副作用に耐えられない場合には、放射線治療を単独で行います。
食道がんへの放射線治療の場合、比較的、多く見られる副作用には、口内炎や食道炎、骨髄抑制、肺炎などがあります。食道からの出血や食道潰瘍などが起こることもありますが、頻度は稀です。
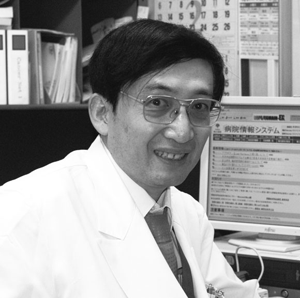
唐澤 克之(からさわ・かつゆき)
1959年東京生まれ。東京大学医学部卒業後。1986年スイス国立核物理研究所客員研究員。1989年東京大学医学部放射線医学教室助手。1993年社会保険中央総合病院放射線科医長。1994年東京都立駒込病院放射線科医長となり、2005年より現職。専門は放射線腫瘍学。特に呼吸器がん、消化器がん、泌尿器がん。日本放射線腫瘍学会理事、日本頭頸部腫瘍学会評議員、日本ハイパーサーミア学会評議員。近著に『がんの放射線治療がよくわかる本』(主婦と生活社)などがある。










