第17回 がんの放射線治療の副作用とその対策
~がん種別の最新の放射線治療と副作用 その⑥ 大腸がん~
放射線が持ち合わせる電離作用を駆使して悪性腫瘍を制御する放射線治療は、同時に正常細胞にもダメージを与え、さまざまな有害反応(副作用)を引き起こすことがあります。それでも、現在の放射線治療では、がん病巣への的確な照射が可能になり、放射線障害が確実に減少しています。したがって、放射線治療を始める前から、必要以上にその副作用を心配する必要はありません。
しかしながら、放射線治療についての正しい知識を持ち合わせ、治療後に発症する重い副作用を認識しておかなければ、大事な症状を見逃してしまいがちです。定期的な診察で早期発見に努めるとともに、いざというときの対処法を心得ておくことが、放射線治療を受けるうえでの得策だと言えます。
そのような趣旨で連載している17回目は、「がん種別の放射線治療と副作用」として大腸がん・肛門がんを取り上げます。ぜひ、副作用対策にも役立てていただきたいと思います。
海外では肛門括約筋の温存をはかるため、術前・術後の照射を積極的に併用
今回、取り上げる大腸がんは、直腸・結腸・盲腸にできるがんの総称で、女性よりも男性に多いのが特徴です。年齢別罹患率は、50歳代から増加し、高齢者ほど高い傾向が見られます。
大腸がんの手術は、早期の場合には、内視鏡的治療と外科的手術治療とに分けられます。進行・再発がんの場合には、直腸がんの局所再発であれば外科的手術治療の適応は少なくとも術前に根治が期待できることが原則です。
また、大腸がんの抗がん剤治療には、進行がんの手術後に再発予防を目的とした補助化学療法と、根治目的の手術が不可能な進行・再発がんに対する生存期間の延長およびQOL(生活の質)の向上を目的とした治療法があります。
そして、大腸がんの放射線治療ですが、術後の再発抑制や術前の腫瘍量減量、切除不能転移・再発大腸がんの症状の軽減を目的とした緩和的放射線療法、肛門温存を目的とした補助放射線療法などがあります。
大腸がんのうち、結腸がんでは、緩和を目的としたケース以外に放射線治療が行われることは稀です。それに対し、直腸がんでは緩和的照射以外にも、術前照射や術後照射が用いられるケースが多々あります。
大腸がんの治療は、あくまで手術が基本です。それでも海外では、術前・術後の照射を積極的に併用しています。そのことで手術による切除範囲を少なくして、肛門括約筋の温存をはかるのです。
術前照射と術後照射は化学療法との併用が基本
直腸がんに対して放射線治療が行われるのは、主に次のようなケースです。
1つ目の術前照射は、手術前にがんを縮小させることで、切除範囲をより小さくし、肛門の機能を温存するのが目的です。2つ目の術後照射は、再発防止が目的です。3つ目は、手術の対象にならない大きながんに対する術前照射です。4つ目は切除不能な進行がんに対する緩和的照射で、痛みを和らげるために使います。その他、手術の際、切除した端の部分にがん細胞が認められたときには、術中照射が行われています。
術前照射は、骨盤全体に行われます。その際、放射線に弱い小腸への線量を抑制するため、うつ伏せの状態で照射します。体の固定は必ずしも必要ありませんが、固定具が用いられることもあります。
その照射は右と左、後方からの3門照射、または前後左右からの4門照射が中心になります。ちなみに、がんが再発した場合には、高線量率の組織内照射が行われることがあります。
照射する線量は、術前照射の場合には40~50Gyを20~28回に分ける通常分割照射が標準になります。その一方、術後照射も50Gyを20~28回に分けるのが標準的ですが、手術でがんを完全に切除できなかったことが明らかな場合には、できる限り腸管を照射範囲からはずして60Gyまで照射します。
術中照射では、電子線が使用されます。その照射線量は切除した端の部分にどの程度、がん細胞が見られるかによって違ってきます。ただし、がんが肉眼でもわかる場合には20Gyが、顕微鏡でなければわからない程度であれば15Gyが標準になります。
術前照射と術後照射は化学療法との併用が基本で、抗がん剤としてはフルオロウラシルを用いるのが基本です。また、治療部位にがんが再発した場合、温熱療法を併用すると効果が上がることがあります。
こうした直腸がんへの放射線治療の副作用としては、早期であれば下痢や吐き気、膀胱炎、肛門痛などが見られます。いずれも時間が経つにつれて自然に治ることが多いのですが、フルオロウラシルと併用した場合、稀に重度の下痢が起こることがあります。
放射線治療や化学療法の効果アップ・副作用の軽減などを目的として併用される温熱療法
先程、「治療部位にがんが再発した場合、温熱療法を併用すると効果が上がることがある」と記しました。その「がんの温熱療法」は、「ハイパーサーミア」とも称されています。
がん細胞は、正常細胞に比べて熱に弱く、42・5℃になると死滅してしまう性質があります。ハイパーサーミアは、その性質を利用し、体を加熱することでがんを治そうとする温熱療法です。
「自然治癒したがん患者の3分の1が発熱をしていた」という報告などから、がんが熱に弱いのではないかという推測は、かなり以前からありました。
温熱療法が本格的に研究され始めたのは1960年代に入ってから。現在は、いくつかの医療機関で温熱療法が行われています。ただし、温熱療法は基本的には研究段階に留まり、他の治療法では根治が難しい局所進行がんや再発がんが主な対象となっています。
現在、一般に行われている温熱療法は、電磁波を用いてがんとその周辺を温める局所温熱療法です。それは体の前後に電極を置き、電磁波を発生させて行います。
体表面に近いがんは、目的の温度まで比較的、容易に温めることができます。しかし、深奥部にあるがんは、脂肪や空気が邪魔をして十分に温めるのが難しく、十分な効果を得られないことがあります。加えて、過熱によって火傷を起こすこともあります。
温熱療法が単独でがん治療に用いられることは稀で、放射線治療や化学療法の効果を高めることや、副作用の軽減などを目的として併用されます。比較的多いのは、放射線治療との併用で、脳腫瘍や食道がん、乳がんなど、いくつかのがんで温熱療法が試みられています。
温熱療法で満足のいく効果が得られているがんはまだ少数です。それでも、悪性中皮腫や骨・軟部腫瘍では、症例にもよりますが、きわめて高い効果が得られることがあります。たとえば、悪性中皮腫で胸水が溜まっている患者さんに対し、放射線治療と化学療法、温熱療法を組み合わせると、胸水が消えてQOLが大きく向上します。根治に至らないものの、何度でも同じ治療を繰り返せるので、QOLの向上とともに、生存期間の延長が期待できます。
QOLを重視し、まず化学放射線療法を行う
肛門がんは、肛門の入り口から約3㎝にわたる管状の部分(肛門管)に生じるがんの総称です。大腸がんに比べ、その頻度は稀です。がんの発育形式は、肛門管のなかから発生した管内型と、肛門管の外から発生した管外型に分類されます。一般に肛門がんは60~70歳代に多く発生するとされています。
患者数は少ないものの、肛門がんでは化学放射線療法が手術と同等の治療成績をあげていて、人工肛門を造らなくても根治が見込めます。日本においては手術の治療成績が欧米よりも優れているので、術前・術後照射は標準的な治療法となっていませんが、肛門の機能温存を望む患者さんは少なくありません。したがって、今後、放射線治療が選択される比率は高くなると推察されています。
肛門がんの場合、がんの大きさが2㎝以下であれば、放射線治療単独で治療が可能です。それ以上の大きさの場合には化学放射線療法が行われます。以前は手術による治療が中心でしたが、そのケースでは、がんが肛門括約筋まで浸潤していると人工肛門の造設が避けられなくなります。
その一方で、これまでの研究により、化学放射線療法は手術と同等の効果が期待できることがわかっています。そのため、現在ではQOLを重視し、まず化学放射線療法を受け、がんが完全に消失しなかった場合や再発した場合に手術で対処するという方法が一般的になっています。
がんが完全に消失した場合は、当然、人工肛門の必要はありません。また、がんが残った場合でも、がんが小さければ人工肛門を造らずにすむ可能性があります。
肛門がんの放射線治療の場合、総線量45~60Gyを、1回あたり1・8~2・0Gyに分けて照射するのが標準的です。その際、前後対向2門照射で、鼠径部を含めた全骨盤照射を行うのが一般的です。また、治療の途中からは股関節や大腿骨頭部への線量を減らすように工夫します。なお、化学放射線療法で使われる抗がん剤は、フルオロウラシルとマイトマイシンCの併用が基本になっています。
また、化学放射線療法による局所制御率は70~90%、5年生存率は65~90%と言われています。
肛門がんの放射線治療における副作用としては、下痢や血便、食欲不振などの消化器症状以外にも、放射線宿酔、膀胱炎などが起こることがあります。その多くの場合、症状は軽度なので、薬による対症療法で対処が可能です。
なお標準治療確立のため、現在、肛門管がんの化学放射線療法の臨床試験を行っておりますので、詳しくは当方までお問い合わせください。
■都立駒込病院放射線科
03–3823–2101
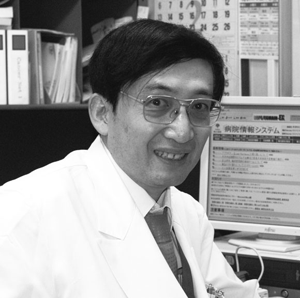
唐澤 克之(からさわ・かつゆき)
1959年東京生まれ。東京大学医学部卒業後。1986年スイス国立核物理研究所客員研究員。1989年東京大学医学部放射線医学教室助手。1993年社会保険中央総合病院放射線科医長。1994年東京都立駒込病院放射線科医長となり、2005年より現職。専門は放射線腫瘍学。特に呼吸器がん、消化器がん、泌尿器がん。日本放射線腫瘍学会理事、日本頭頸部腫瘍学会評議員、日本ハイパーサーミア学会評議員。近著に『がんの放射線治療がよくわかる本』(主婦と生活社)などがある。








