第22回 がんの放射線治療の副作用とその対策
~がん種別の最新の放射線治療と副作用 その⑪ 肝がん~
放射線が持ち合わせる電離作用を駆使して悪性腫瘍を制御する放射線治療は、同時に正常細胞にもダメージを与え、さまざまな有害反応(副作用)を引き起こすことがあります。それでも、現在の放射線治療では、がん病巣への的確な照射が可能になり、放射線障害が確実に減少しています。したがって、放射線治療を始める前から、必要以上にその副作用を心配する必要はありません。
しかしながら、放射線治療についての正しい知識を持ち合わせ、治療後に発症する重い副作用を認識しておかなければ、大事な症状を見逃してしまいがちです。定期的な診察で早期発見に努めるとともに、いざというときの対処法を心得ておくことが、放射線治療を受けるうえでの得策だと言えます。
そのような趣旨で連載している22回目は、「がん種別の放射線治療と副作用」として、難治性がんの一つに数えられる肝がんを取り上げます。ぜひ、副作用対策にも役立てていただきたいと思います。
発見時は病状が進んでいることが多い
今回、着目したがん種である肝がんには多くの種類があります。その大部分は肝細胞がんで占められています。
肝がんは、肝臓にできた原発性肝がんと別の臓器から転移した転移性肝がんに大別されます。原発性肝がんには、肝臓の細胞ががんになる肝細胞がんと、胆汁を十二指腸に流す胆管の細胞ががんになる胆管細胞がん、肝細胞・胆管細胞混合がん、未分化がん、胆管嚢胞腺がん、神経内分泌腫瘍、小児の肝がんである肝細胞芽腫などがあります。
国内では原発性肝がんのうち肝細胞がんが約90%を占めていて、一般に肝がんというときは、肝細胞がんを指します。また、肝がんは、肺がんや子宮頸がんと並び、主要な発生要因が明らかになっているがんの一つです。そのなかで最も肝心なのは肝炎ウイルスの持続感染で、それによって肝細胞で長期にわたって炎症と再生が繰り返されるうちに遺伝子の突然変異が積み重なり、肝がんへの進展に重要な役割を果たすと考えられているのです。
肝炎ウイルスにはA・B・C・D・Eなどさまざまな種類が存在していますが、肝がんと関係があるのは主にBとCです。日本では、肝がんの約60%がC型肝炎ウイルスの持続感染、約15%がB型肝炎ウイルスの持続感染に起因するとされています。
B型・C型肝炎ウイルスに感染すると、B型肝炎では約10%、C型肝炎では約70%の割合で慢性肝炎に至ります。そして、炎症が続くことで肝臓の繊維化が進み、肝硬変を経て肝がんになるのが典型的なパターンです。
肝臓は「沈黙の臓器」と言われています。これは何らかの原因で肝臓が障害を受けても、予備能力が高いため、症状として自覚できないことが多いからです。そのため、肝がんが発見されたときには肝機能が著しく低下していることが少なくなく、治療法の選択が制約されがちです。
肝臓は放射線に弱い臓器だが、線量集中性のよい治療法で根治性も出てくる
肝がんの最も根治性の高い治療法は、手術による病巣の切除です。しかし、肝がんは病巣を切除しても残された肝臓に新たながんが発生することが多いので、近年は手術による切除の比率は低下しています。
手術に次ぐ治療の選択肢は、肝動脈塞栓術、経皮的エタノール注入法、マイクロ波凝固術、ラジオ波焼灼術などのIVR(体内にカテーテルや針を入れて行う治療法)です。放射線治療はIVRを中心とした集学的治療の一つとして位置づけられています。
肝動脈塞栓術とは、肝動脈の内部に小さなゼラチンスポンジを詰めて血流を遮断し、がん細胞への栄養供給源を断つことで、がん細胞を死滅させる治療法です。
経皮的エタノール注入法は、がんに血液を運んでいる動脈に針を挿し、その先端からエタノールを注入することで、がん細胞を壊死させる治療法です。
マイクロ波凝固術は、がんの腫瘍に電極を差し込み、先端からマイクロ波(電子レンジと同じ電波)を照射し、がんを加熱し凝固・壊死させる治療法です。
ラジオ波焼灼術は、がんの腫瘍に電極を差し込み、先端からラジオ波(AMラジオと同じ電波)を照射し、がんを焼き切る治療法です。
しばらく前まで、放射線治療が選択されるのは、主にIVRが苦手とする大きながんができている場合や、腫瘍塞栓(がんが血管内に入り込んで血流と逆方向に増殖するもの)ができている場合で、がんの消失を目的として行われていました。
肝臓は放射線に弱い臓器なので、正常な部分の機能を維持し、なおかつがんに十分な線量を照射できるように注意しなければなりません。腎臓や胃、十二指腸、脊髄などの周辺臓器への線量にも注意が必要です。
また、呼吸によって肝臓が動くため、できるだけ呼吸に応じた照射を行います。それができない場合は、呼吸による移動量を見越して照射範囲を広く確保します。
最近では、固定精度をよく保ち、1回の線量を大きくし、数回の治療で、小型の肝がんを治癒させる定位放射線治療という技術もより広く用いられ始め、良好な局所制御効果と生存率が得られるようになってきています。
肝がん放射線治療の方法と線量分割
肝がんに対する放射線治療は、がんに放射線を集中して正常臓器への線量を減らすために、できるだけ多方向から照射するのが原則です。しかし、肝がんでは、肝臓自体が最大のリスク臓器なので、単に正常組織への線量を低くするだけでなく、放射線が当たる部分をできるだけ少なくしなければなりません。そのため、照射方向を増やすよりも、1~2方向から照射するほうが得策となるケースも少なくありません。肝がんの占拠部位、肝臓の予備能力および肝がん治療の目的(根治的か緩和的か)などによって適切に判断します。
肝がんに対する線量分割は、1回あたり2Gyの通常分割照射が標準的でした。そして、総線量は肝機能の状態や照射範囲、照射法によって異なり、がん周辺だけに照射するときは50Gy前後、肝臓全体に照射するときは30Gy程度が目安になります。しかし最近の腫瘍に線量を集中できる定位照射線治療を用いる場合には腫瘍の部分には1回8Gyという線量を5回程度(40Gy程度)を照射して、生物学的な効果を高めて治療します。
肝がんに対する粒子線治療
肝がんに対しては、陽子線・重粒子線(炭素イオン線)といった粒子線治療も比較的、よい成績をあげています。
陽子線や重粒子線は体内に入るとある一定の深さで完全に止まり、その際に大きなエネルギーを発生してがん病巣にだけ電離を起こしたり、がん細胞の遺伝子を直接破壊したりします。この特徴は「ブラッグピーク」と呼ばれています。
また、水素原子から電子を取り去ると1個の陽子が残ります。その陽子を加速器で光速に近い速度まで加速し、がんに向かって照射するのが陽子線治療です。それと、水素よりも重い原子核の流れを総称して重粒子線と呼びます。重粒子線には、炭素やネオン、シリコン、アルゴンなどがあります。ただし、現在、実用化されているのは炭素線だけで、通常、がん治療の領域で重粒子線という場合には炭素線を指すのです。
この粒子線治療の治療対象となるのは、主にがんの個数が少なく(3個以下)、消化管から離れていて、肝臓以外にがんがなく、肝機能がある程度保たれている場合です。ただし、がんの数については、一定の照射範囲に収まる場合には、いくつあっても治療が可能です。
照射線量や照射回数などは、患者さんによって、また医療機関によって異なります。それでも、基本的には通常の放射線治療よりも1回の線量が多く、照射回数は少なくてすみます。
主な副作用は、吐き気・食欲不振・消化管出血など
肝がんに対する放射線治療の成績ですが、腫瘍塞栓に対する放射線治療の奏功率は約85%です。この数字は、腫瘍塞栓のある患者さんの予後を大きく改善したと言えます。また、肝臓そのものにあるがんに対しては、IVRと併用で60~70%の奏功率が期待できます。
先述のX線による定位放射線治療、陽子線治療や重粒子線治療では局所制御率が90%と高く、肝機能がある程度維持されている患者さんでは5年生存率が50~60%と、手術とほぼ同等の成績を収めています。ただし、生存率はがんの数や肝機能の状態によって左右され、とりわけ肝機能の状態が悪い場合は成績が著しく低下します。
放射線治療による副作用ですが、肝障害のために吐き気や食欲不振などが起こることがあります。また、消化管出血、肝炎ウイルスの再活性化が起こることもあります。
また、正常な肝臓へ広範囲に放射線が照射された場合、肝機能が低下することがあります。それは、通常、照射から6カ月から1年後に見られます。しかし、治療医は、肝臓の耐容線量の値を知っていますので、過剰照射による機能障害や機能不全に陥ることはめったにありません。
放射線治療による肝機能障害の多くは、採血による肝機能検査値に変化が出る程度です。高線量の照射による肝臓の損傷が大きくなると、倦怠感や黄疸、食欲不振、吐き気・嘔吐などの症状が起こります。このような症状が現れたときは、十分な安静と栄養バランスのよい食事と禁酒が大切です。
吐き気のあるときは、たとえば次のような工夫を凝らすことができます。
消化のよい食事を少量ずつ、回数を多くして食べる。
油で揚げたものや脂肪の多いものは控える。
吐き気を誘うような匂いの強いもの・熱いものは避ける。
食前に番茶やレモン水などでうがいをしたり、食事中に冷たいものを飲んだりして、吐き気を予防する。
先述のように、肝がんの治療では、肝臓の入り口(肝門部)に照射した後で、十二指腸潰瘍による消化管出血が起こることがあります。基礎疾患の肝硬変による門脈圧亢進症(肝臓に通じる栄養血管の圧力上昇)があるとその危険性が高まります。
いずれにしても、肝がんへの放射線治療では、基礎にあるがん自体の影響も加わって、ときに重い副作用が起こる恐れがあります。ですから、実際に治療を受けるときは、担当医から十分な説明を受けることが大切です。
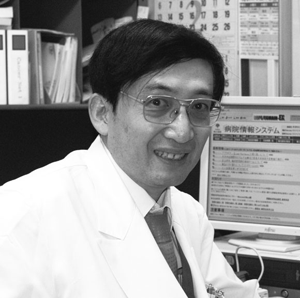
唐澤 克之(からさわ・かつゆき)
1959年東京生まれ。東京大学医学部卒業後。1986年スイス国立核物理研究所客員研究員。1989年東京大学医学部放射線医学教室助手。1993年社会保険中央総合病院放射線科医長。1994年東京都立駒込病院放射線科医長となり、2005年より現職。専門は放射線腫瘍学。特に呼吸器がん、消化器がん、泌尿器がん。日本放射線腫瘍学会理事、日本頭頸部腫瘍学会評議員、日本ハイパーサーミア学会評議員。近著に『がんの放射線治療がよくわかる本』(主婦と生活社)などがある。








