第35回 がんの放射線治療の副作用とその対策
~主な適応と照射範囲の設定法 その⑨ 白血病の全身照射~
放射線が持ち合わせる電離作用を駆使して悪性腫瘍を制御する放射線治療は、同時に正常細胞にもダメージを与え、さまざまな有害反応(副作用)を引き起こすことがあります。それでも、現在の放射線治療では、がん病巣への的確な照射が可能になり、放射線障害が確実に減少しています。したがって、放射線治療を始める前から、必要以上にその副作用を心配する必要はありません。
しかしながら、放射線治療についての正しい知識を持ち合わせ、治療後に発症する重い副作用を認識しておかなければ、大事な症状を見逃してしまいがちです。定期的な診察で早期発見に努めるとともに、いざというときの対処法を心得ておくことが、放射線治療を受けるうえでの得策だと言えます。
そのような趣旨で連載している35回目は「白血病の全身照射」を取り上げ、その特徴と治療方法について最新の知見を交えて概説します。ぜひ、副作用対策にも役立てていただきたいと思います。
骨髄移植の前処置として行われる全身照射が大部分
白血病は「血液のがん」と称される血液疾患で、がん化した造血細胞が骨髄で自律的に増殖して正常な造血を阻害し、多くは骨髄のみに留まらず、末梢血液中にも造血細胞が溢れ出てきます。
白血病には、さまざまな種類があります。大別するとがん化した細胞が急速に増殖する急性、がん化した細胞がゆっくりと増殖する慢性があります。そして、急性には急性骨髄性白血病・急性リンパ性白血病、慢性には慢性骨髄性白血病・慢性リンパ性白血病があります。
白血病に対する放射線治療は、骨髄移植の前処置として行われる全身照射が大部分です。全身照射はいずれの白血病も対象となり、シクロホスファミドなどの抗がん剤と併用されます。
全身照射の目的は二つあります。一つは、白血病細胞の死滅。もう一つは、リンパ球の不活性化による拒絶反応の抑制。ただし、抗がん剤治療だけでそれらを行うこともあります。しかし、放射線治療には、大部分の抗がん剤と交叉耐性(ある生物が1種類の薬剤に対して耐性を獲得すると同時に、別の種類の薬剤に対する耐性も獲得すること)がありません。加えて、放射線治療は、全身のどの部位でも対象となりますし、危険臓器を避けて照射できます。これは抗がん剤治療にはない特長です。
全身照射にはさまざまな工夫が凝らされる
白血病に対する全身照射では、リニアック(放射線治療装置)の最大照射範囲が、通常、40㎝四方しかなく、いっぺんに全身を照射するには何らかの工夫を凝らさなくてはいけません。そのため、①放射線ビームを水平方向から出す(長SAD法)、②照射装置を回転させる、③治療用ベッドを移動させるなどの方法がとられています。
「①」の放射線ビームを水平方向から出す方法は、照射装置と患者さんとの間に十分な距離を保つ必要がありますが、十分な広さの治療室さえあれば、他の装置が必要ないため、最も多く用いられています。
照射法は、「①」の場合、仰向けの姿勢で左右から2門照射、または立位で前後から2門照射を行います。「②」の照射装置を回転させる方法と、「③」の治療用ベッドを移動させる方法は、前方1門、または前後対向2門照射が行われます。
白血病に対する放射線の照射は、従来、1回照射が中心でしたが、現在では、総線量12Gyを1回2Gyで、1日2回照射するのが通常です。
白血病への放射線治療の主な副作用は、骨髄移植自体で起こる副作用に隠れてしまうことがありますが、急性期には放射線肺臓炎(間質性肺炎)が、晩期としては白内障や腎障害が、それぞれ代表的なものです。また化学療法と併用しているので、2次性発がん(抗がん剤や放射線による正常細胞の障害のために、治療を終えた数年から数十年後に生じる「元の病気とは別の種類のがん・白血病」)の発生も挙げられます。また、間質性肺炎に備えて肺への線量を低く抑えることも重要です。
先述のように全身照射には工夫が凝らされ、副作用の防御方法は進歩してきています。ですから、副作用は軽度になっています。それほど心配はいりませんが、2次性発がん・間質性肺炎・白内障・腎障害以外にも、可能性のある副作用を記しておきます。
急性期(全身照射の期間および終了後しばらく)は、悪心や嘔吐、口の渇き、脱毛、下痢、涙の減少、肝障害、耳下腺炎……などです。晩期は、ホルモン障害、成長遅延、性腺障害……などです。
小児白血病などの「治療の実際」と「主な副作用」
「白血病」と言えば、子どものがんでは最も多く、全体の約40%を占めています。近年、奏功率の高い抗がん剤の登場で生存率が高くなってきていますので、この領域での放射線治療の比重は減りつつあります。
それでも成人の白血病同様、主に骨髄移植の前処置としての全身照射が行われています。加えて、中枢神経への再発予防や、骨髄外に再発した際にも放射線治療が行われます。
中枢神経への再発予防では、頭蓋骨全体に放射線を照射します。その総線量は6歳以上の子どもの場合が18Gyで、1回1・5~1・8Gyに分けて照射します。6歳以下の子どもには12Gyを8回に分割します。
骨髄外の再発に対しては、精巣の場合、総線量を24~25Gyとして12~13回に分けて照射します。また、中枢神経への再発予防の際の放射線照射では、その副作用として成長障害や性的成熟障害、知能障害などの可能性があります。ただし、総線量を18Gyに抑えることで、その大部分は防げるようになっています。また、白血病での骨髄移植前の全身照射では、分割して照射することで成長障害などのリスクを軽減できます。
個々の患者さんにより その適応・方法は異なる
今回、フォーカスした白血病の領域では、近年、著しい治療技術の進歩によって、それまで太刀打ちできないでいた白血病、あるいは悪性リンパ腫などの造血器腫瘍の治癒率が上がってきました。とりわけ、骨髄移植は多くの患者さんにベネフィット(恩恵)をもたらしています。
骨髄移植は、提供者(ドナー)の正常な骨髄細胞を静脈内に点滴で注入して移植する治療です。ちなみに骨髄移植には造血幹細胞が用いられますが、その造血幹細胞は末梢血幹細胞や臍帯血など、骨髄以外にも入手方法が多様化しているため、それらを「造血幹細胞移植」と総称することもあります。
その造血幹細胞移植の前処置として、病んだ骨髄細胞を根絶するために抗がん剤や放射線が用いられるわけです。放射線治療は殺細胞効果がきわめて高いので、病んだ骨髄の細胞を叩くには適した治療方法だと言えます。それでも、単独では不十分で化学療法と併用するのです。
いずれにしても、全身照射は骨髄移植の前処置としてきわめて有効です。ただし、個々の患者さんによりその適応や方法が違います。主治医や放射線科医によく相談してから全身照射に臨むことをお勧めします。
新しい全身照射の方法について
ここで、今回は白血病の造血幹細胞移植の前処置の照射技法に新しい方法が開発されつつある点をお示ししておきます。
従来の放射線治療では、体の組織への放射線の線量を均一に投与することしかできませんでした。ところが、最近では照射野内の線量に強弱をつけて照射ができるようになり、線量を不均一に投与することが可能になりました。その技術を強度変調放射線治療と呼びます。そしてトモセラピー(Tomo Therapy)という装置を用いると、その装置が患者さんの体の体軸方向へ移動させながら、体の中に投与される線量を自由に変調させて、全身照射を行うことができます。
全身照射の限界として、これまでは肺や腎臓などの放射線に対して感受性の高い臓器があるために、自ずとそれを超えるような線量投与ができませんでした。そこへこの装置を用いて全身照射を行うと、全身の臓器の線量を自由に変えることが可能になり、肺や腎臓など線量を低下させる必要のある臓器の線量を任意のレベルまで低下させることができます。
多くの施設で行っているLong SSD法という従来の方法では、肺の線量は低下させられますが、その前後の組織の線量も下げてしまうとされ、それを補うため、いろいろな処置を講じなければならないというデメリットが生じます。
さらに考えを進め、白血病細胞の確率密度分布は体内で一定ではなく、当然のことながら差があります。白血病細胞は一般に骨髄やリンパ組織により数多く分布しています。その一方で、肺や腎臓、消化管、心臓など多くの正常臓器では相対的に少なく分布しています。よって、数多く分布している臓器に高線量を照射し、少なく分布している臓器の線量を低減させることができれば、より合理的な全身照射を行えるのです。
トモセラピーは体内のあらゆる部位の線量を任意に調節できるため、そのような照射が可能になるのです(この方法を全骨髄照射TMIもしくは全骨髄リンパ節照射TMLIと呼んでいます)。
全骨髄照射は二つのメリットがあります。すなわち正常臓器の線量を低減できるので、全身照射が必要な症例の適応年齢を上げることができます。通常、根治的な全身照射の適応年齢は50歳までとされていますが、それが60歳程度までは適応とできると考えられています。
また、正常臓器の線量を低減できると同時に、骨髄への投与線量も増加させることができることから、現在では末梢血に白血病細胞がない状態(寛解状態)が移植の良い適応とされています。けれども、実際にはそうでない症例(非寛解状態)も少なくないため、それら症例に対する移植の適応が増える可能性もあります。
現在、私たちの施設では、全国に先駆け、全骨髄照射の線量増加の臨床試験を行っています。数年後には一般的な治療として広く受け入れられる治療になることを期待しています。
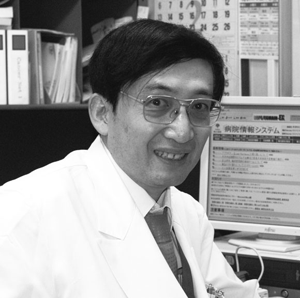
唐澤 克之(からさわ・かつゆき)
1959年東京生まれ。東京大学医学部卒業後。1986年スイス国立核物理研究所客員研究員。1989年東京大学医学部放射線医学教室助手。1993年社会保険中央総合病院放射線科医長。1994年東京都立駒込病院放射線科医長となり、2005年より現職。専門は放射線腫瘍学。特に呼吸器がん、消化器がん、泌尿器がん。日本放射線腫瘍学会理事、日本頭頸部腫瘍学会評議員、日本ハイパーサーミア学会評議員。近著に『がんの放射線治療がよくわかる本』(主婦と生活社)などがある。










