第15回 がんの放射線治療の副作用とその対策
~がん種別の最新の放射線治療と副作用 その④ 肺がん~
放射線が持ち合わせる電離作用を駆使して悪性腫瘍を制御する放射線治療は、同時に正常細胞にもダメージを与え、さまざまな有害反応(副作用)を引き起こすことがあります。それでも、現在の放射線治療では、がん病巣への的確な照射が可能になり、放射線障害が確実に減少しています。したがって、放射線治療を始める前から、必要以上にその副作用を心配する必要はありません。
しかしながら、放射線治療についての正しい知識を持ち合わせ、治療後に発症する重い副作用を認識しておかなければ、大事な症状を見逃してしまいがちです。定期的な診察で早期発見に努めるとともに、いざというときの対処法を心得ておくことが放射線治療を受けるうえでの得策だと言えます。
そのような趣旨で連載している15回目は、「がん種別の放射線治療と副作用」として肺がんを取り上げます。ぜひ、副作用対策にも役立てていただきたいと思います。
非小細胞肺がんの治療選択肢
肺がんは非小細胞肺がんと小細胞肺がんの2つに大別できます。それぞれの性質が異なるため、治療法も違ってきます。
非小細胞肺がんの病期はⅠ~Ⅳ期に分けられ、さらにⅠ~Ⅱ期はそれぞれAとBの2段階に細分化されます。非小細胞肺がんは、肺がん全体の80%以上を占め、小細胞肺がんに比べて増殖のスピードが緩やかな反面、放射線感受性が低いという特徴があります。
切除可能であれば手術が第1選択肢となるので、Ⅰ~Ⅱ期では、放射線治療が第1選択となることは患者さんが手術を拒否するような場合に限られます。対象となるのは、ⅢA期とⅢB期です。ただし、ⅢB期において、原発巣ではない肺門部にリンパ節転移がある場合や、胸水が見られる場合には対象となりません。
また、Ⅰ~Ⅱ期のがんでも、高齢者や合併症のリスクが高い人に対しては、根治を目的とした放射線治療が行われます。昨今、リンパ節転移を伴わない早期がんに対し、定位放射線治療が行われるケースが増え、優れた成績をあげています。その対象となるのは最大径が5㎝以内で、リンパ節転移や遠隔転移がないⅠ~Ⅱ期です。
その他、呼吸困難などの症状緩和や延命を目的として放射線治療が行われることも多く、根治が見込めない進行がんに対しても、放射線治療は大きな役割を果たしています。
なお、がんの縮小を目的とした術前照射や再発予防のための術後照射が行われることもあります。ただし、その有効性はまだ明らかになっていません。
非小細胞肺がんへの照射方法
非小細胞肺がんに対する放射線治療は外部照射が基本ですが、早期がんに対しては腔内照射が行われることもあります。
一般的な外部照射では、がんと転移が見られる周辺リンパ節を標的として照射します。また、多くの場合、CTなどで転移が確認できなくても、転移の疑いがあるリンパ節も、再発予防のために照射範囲に含めます。そして、呼吸による臓器の移動などに備え、1・5~2・5㎝程度のマージンをとります。
ただし、このような予防的リンパ節照射は、放射線肺炎などの副作用のリスクを高め、再発率が予防的リンパ節照射を行わない場合と変わらず、生存率がむしろ低くなるという報告もあります。現時点では、予防的リンパ節照射の有無と治療成績の関係は明確ではありません。そのため、化学療法と併用する場合には、再発予防効果を抗がん剤に任せ、予防的なリンパ節照射を部分的に省略するケースもあります。
また、定位放射線治療(病巣に対し多方向から放射線を集中させる照射法)は、リンパ節転移がないがんが治療対象です。したがって、照射範囲はがんに限定され、それによる臓器の移動や治療時の位置設定誤差などを考慮したマージンが加えられます。その1回あたりの線量が通常の外部照射より大きいので、照射範囲の設定はCT画像などを用いて慎重に行われます。一般に、呼吸性移動によるマージンに、さらに5㎜ほどのマージンを設定して照射されます。
非小細胞肺がんに対する放射線治療では、前後対向2門照射で40~45Gyまで照射した後、斜入対向2門照射に変更し、脊髄を照射範囲からはずすのが一般的です。その際、脊髄の1回あたりの最大線量が2Gyを超えないように注意します。加えて、がんの縮小に合わせ、照射範囲を縮小しながら治療します。
定位放射線治療では、患者さんに合わせて門数やビームの角度などが決められます。一般には、6門以上による固定多門照射や、リニアックを回転させながら照射する回転照射が用いられます。ちなみに、腔内照射では、イリジウム192などの密封小線源を気管支に挿入して照射します。
非小細胞肺がんへの放射線治療による副作用
通常の外部照射では、がんの大きさによって総線量が違ってきます。肉眼で判別できるほどの大きさなら、60Gy以上の線量が必要になりますが、顕微鏡でわかる程度の微小ながんであれば、40~50Gyで十分です。いずれの場合も、1回あたり2Gyの通常分割照射が基本です。ただし、最近は1回あたりの線量を減らし、1日2回照射する過分割照射法も行われています。
定位放射線治療では、1回あたり12Gyを4回に分けて照射する方法が一般的ですが、1回10~15Gyで4~5回、照射することもあります。一方、腔内照射については、標準的な線量分割が確立していないのが実情で、高線量率照射では40Gyを20回に分けて外部照射を行った後、腔内照射で週1回6Gyの照射を3回行うことが多いようです。
また、進行がんに対する化学放射線療法では、シスプラチンを中心とした抗がん剤との併用が一般的です。放射線治療と化学療法を行うタイミングとしては、副作用のリスクが高くなりますが、相乗効果の高さから同時併用が標準的です。
先述のように、非小細胞肺がんでは、手術が第1選択肢となるのは、基本的にⅠ~Ⅱ期です。したがってⅢ期は手術の対象とならないのですが、化学放射線治療によって治療成績は向上しています。その5年生存率は15~20%です。近年、早期がんに対する放射線治療の治療成績も向上が著しく、Ⅰ期のがんに対する定位放射線治療の5年生存率は50~70%となっています。
非小細胞肺がんに対する放射線治療の主な副作用には、食道炎や肺炎、全身倦怠感、食欲不振、皮膚炎などが見られます。化学放射線治療では、副作用が強くなりがちなので注意が必要です。肺炎は照射範囲内に収まっていれば重症化することは少ないのですが、照射範囲よりも外に広がっている場合には重症化しやすくなります。また、パクリタキセルやドセタキセルを併用した場合には、心障害が起こりやすくなります。
小細胞肺がんの治療選択肢と照射方法
非小細胞肺がんと比べて小細胞肺がんは進行が速く、がんとの診断を受けたときは、リンパ節転移や遠隔転移を起こしていることが多いという特徴を持っています。そのため手術で切除できるケースは少なく、また放射線や抗がん剤が効きやすいことから、放射線治療と化学療法、化学放射線療法が標準的な治療法になっています。
小細胞肺がんは、がんが片側の肺と周辺のリンパ節に留まっている限局型と、肺の外にまで広がり遠隔転移を起こしている進展型に大別されます。根治的照射の対象となるのは限局型の場合です。ただし、進展型でも遠隔転移したがんが化学療法で消失した場合には、原発巣に対して根治的照射が行われることがあります。
また、小細胞肺がんは脳に転移しやすいため、原発巣の治療が終わった後で、転移を防ぐための予防的全脳照射が行われることがあります。予防的全脳照射は、単に脳に転移する確率を下げるだけでなく、生存率も向上させることがわかっています。そのため、放射線治療でがんが消失、あるいは大幅に縮小した場合には、予防的全脳照射を行うことが標準的治療になっています。そのほか、呼吸困難など、がんの増大による症状の緩和のためにも、放射線治療が行われることがあります。
小細胞肺がんへの放射線治療は一般的な外部照射が中心で、定位放射線治療や腔内照射は行われません。その照射範囲は、がんおよび転移の可能性がある周辺リンパ節を対象とし、それに呼吸による照射部位の移動、治療の際の位置ずれを考慮したマージンを加えた範囲に照射します。
ただし、放射線治療と化学療法を同時に行うケースでは、照射範囲が広くなると副作用のリスクが高まります。治療効果の向上という点では同時併用が良策なのですが、照射範囲が広くなり過ぎる場合には、化学療法でがんを縮小させてから、放射線治療を行うこともあります。また、がんが肺門部から離れた位置にある場合には、がんと肺門部のリンパ節を分け、別々に照射することもあります。
小細胞肺がんへの放射線治療による副作用
小細胞肺がんへの放射線の照射法は、6~10MVのX線を用いて、前後対向2門照射で治療をスタートさせます。その後、斜入対向2門照射に切り替えるなどして、照射範囲から脊髄をはずします。
照射スケジュールとしては、通常分割照射のほか、1日2回照射を行う加速過分割照射があります。小細胞肺がんは増殖のスピードが速いため、がんにダメージから立ち直る隙を与えず、短期間で治療する加速過分割照射のほうが治療成績が優れているのがわかっています。そのため、患者さんの体調がこの方法に耐えられる場合には、こちらが標準になりつつあります。
ただし、脊髄が放射線のダメージから回復するための時間が必要になるので、最低でも6時間以上の間隔をおいて照射しなければなりません。照射線量は、加速過分割照射の場合は、総線量45Gyを1日あたり1・5Gyに分けて3週間で治療するのが標準です。一方、通常分割照射では、45~54Gyを1回あたり1・8Gyに分けるのが一般的です。
また、化学療法を併用するタイミングとしては、放射線治療と並行して実施する同時化学放射線療法が効果の点で優れています。小細胞肺がんの化学放射線療法で使われる抗がん剤としては、シスプラチンとエトポシドを組み合わせたPE療法、イリノテカンとシスプラチンを併用するIP療法が標準的です。シスプラチンとエトポシドは骨髄抑制を、シスプラチンは腎障害を、イリノテカンは肺や食道に障害を起こしやすいという特徴があります。
小細胞肺がんに対する放射線治療の代表的な副作用には、食道炎や肺炎、骨髄抑制などがあります。強力な化学療法と併用するため、早い時期から重症化することが少なくないので注意が必要です。そのほか、食欲不振や全身倦怠感、吐気・嘔吐などが見られることもあります。
晩期の副作用では、放射線治療脊髄症への注意も必要です。
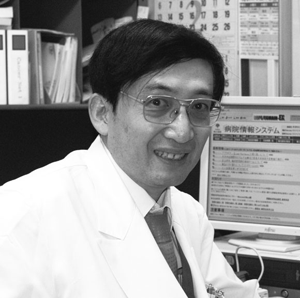
唐澤 克之(からさわ・かつゆき)
1959年東京生まれ。東京大学医学部卒業後。1986年スイス国立核物理研究所客員研究員。1989年東京大学医学部放射線医学教室助手。1993年社会保険中央総合病院放射線科医長。1994年東京都立駒込病院放射線科医長となり、2005年より現職。専門は放射線腫瘍学。特に呼吸器がん、消化器がん、泌尿器がん。日本放射線腫瘍学会理事、日本頭頸部腫瘍学会評議員、日本ハイパーサーミア学会評議員。近著に『がんの放射線治療がよくわかる本』(主婦と生活社)などがある。










